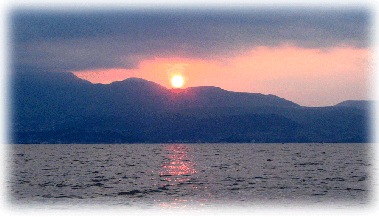
چى•iŒQپG
پ@ˆّ‚«’ھپE’ق‚ê‚ب‚¢“ْپE”é–§‰ï’kپE‘û‚ج‘«پEڈ‰’ق‚èپE‹†‹ة‚جژhگgپE•ْ—¬پE
پ@“V‹C—\‘ھپE‹ض‹هپEژل’ھ
پ@ˆّ‚«’ھ
پ@’n•½‚جŒت‚ًنr‚ك‚é‚و‚¤‚ة–é‚ج’ ‚ھ‰؛‚èژn‚ك‚é‚ئپA”–‰_‚ھٹX‚ج–¾‚©‚ً
‰f‚µڈo‚·پB–ع‚ة‚حŒ©‚¦‚ب‚¢‚ھ‚ئ‚ؤ‚آ‚à‚ب‚‘ه‚«‚بˆّ—ح‚ئ‚¢‚¤چى—p‚ھپA
’ç–h‚جگخ’i‚ًڈ‚µ‚¸‚آکI‚ي‚ة‚µ‚ؤ‚ن‚پB‚س‚¶‚آ‚ع‚حچإŒم‚ج‚ذ‚ئ’ھ‚ًˆô
چA‚س‚©‚“غ‚فچ‚ٌ‚إپA–°‚è‚ةڈA‚¢‚½پB
‰f‚µڈo‚·پB–ع‚ة‚حŒ©‚¦‚ب‚¢‚ھ‚ئ‚ؤ‚آ‚à‚ب‚‘ه‚«‚بˆّ—ح‚ئ‚¢‚¤چى—p‚ھپA
’ç–h‚جگخ’i‚ًڈ‚µ‚¸‚آکI‚ي‚ة‚µ‚ؤ‚ن‚پB‚س‚¶‚آ‚ع‚حچإŒم‚ج‚ذ‚ئ’ھ‚ًˆô
چA‚س‚©‚“غ‚فچ‚ٌ‚إپA–°‚è‚ةڈA‚¢‚½پB
پ@’ھ‚ھˆّ‚‚ة‚آ‚êپAٹC’ê‚ج‚و‚¤‚·‚à”»–¾‚µژn‚ك‚éپB’ھ‚ةڈو‚ء‚ؤ•‚—V‚µ
‚ؤ‚¢‚½•‚‚«‚ھ“ث‘Rژ~‚ـ‚èٹC’†‚ةˆّ‚«چ‚ـ‚ê‚éپB‹›گM‚ئ‘f‘پ‚ٹئ‚ً—§‚ؤ
‚é‚ئپAŒˆ‚ـ‚ء‚ؤچھٹ|‚肵‚ؤ‚¢‚½‚ج‚حپA‘O•û‚ة‚ ‚é”w‚جچ‚‚¢‚ظ‚ٌ‚¾‚ي‚ç
‚جژd‹ئ‚¾‚ء‚½‚µپAڈ¬‹›‚ھ•‚‚«ڈo‚ؤ‚«‚ؤ‚حگg‚ًگِ‚ك‚éچش‚حپA‚ ‚ج‘هٹâ‚ب
‚ج‚¾پB‹¥–\‚ب•كگHژز‚ھگN“ü‚µ‚ؤ—ˆ‚ؤ‚àپAˆêگؤ‚ةچش‚ض“¦‚°چ‚ق‚±‚ئ‚µ‚©
’m‚ç‚ب‚¢•½کaژه‹`ژز‚½‚؟‚ج‘ƒŒA‚¾پB‘هٹâ‚جژüˆح‚حگ´‘|‚ھچs‚«‚ئ‚ا‚«پA
چLڈê‚ھچى‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚±‚إڈ¬‹›‚½‚؟‚ح“ْ‚ًŒˆ‚ك‚ؤ‰½ژ–‚©پA‹cŒˆ‚·‚é
‚ج‚©‚à’m‚ê‚ب‚¢پB
‚ؤ‚¢‚½•‚‚«‚ھ“ث‘Rژ~‚ـ‚èٹC’†‚ةˆّ‚«چ‚ـ‚ê‚éپB‹›گM‚ئ‘f‘پ‚ٹئ‚ً—§‚ؤ
‚é‚ئپAŒˆ‚ـ‚ء‚ؤچھٹ|‚肵‚ؤ‚¢‚½‚ج‚حپA‘O•û‚ة‚ ‚é”w‚جچ‚‚¢‚ظ‚ٌ‚¾‚ي‚ç
‚جژd‹ئ‚¾‚ء‚½‚µپAڈ¬‹›‚ھ•‚‚«ڈo‚ؤ‚«‚ؤ‚حگg‚ًگِ‚ك‚éچش‚حپA‚ ‚ج‘هٹâ‚ب
‚ج‚¾پB‹¥–\‚ب•كگHژز‚ھگN“ü‚µ‚ؤ—ˆ‚ؤ‚àپAˆêگؤ‚ةچش‚ض“¦‚°چ‚ق‚±‚ئ‚µ‚©
’m‚ç‚ب‚¢•½کaژه‹`ژز‚½‚؟‚ج‘ƒŒA‚¾پB‘هٹâ‚جژüˆح‚حگ´‘|‚ھچs‚«‚ئ‚ا‚«پA
چLڈê‚ھچى‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚±‚إڈ¬‹›‚½‚؟‚ح“ْ‚ًŒˆ‚ك‚ؤ‰½ژ–‚©پA‹cŒˆ‚·‚é
‚ج‚©‚à’m‚ê‚ب‚¢پB
پ@‹¥–\‚ب•كگHژزپA‚±‚±‚إ‚حƒXƒYƒL‚ھ•M“ھ‚¾پB‹°‚ê‚ًٹw‚ٌ‚إ‚¢‚ب‚¢ڈ¬‹›
‚ھٹC–ت‚ة—V‚ر‚ةڈo‚é‚ج‚ً‘ز‚؟چ\‚¦‚½‚و‚¤‚ةپA”w•h‚ھ“ف‚¢‰¹‚ً‹؟‚©‚¹ٹC
–ت‚إ‚®‚é‚è‚ئˆê“]‚µپA‚ذ‚ئ“غ‚ف‚·‚éپBڈ¬‚³‚بˆ£‚µ‚ف‚ج—ض‚ھ’ç–h‚جچغ‚ـ
‚إٹٌ‚¹‚ؤ‚‚éپBژ‚ة‚ح‘ه’_•s“G‚ة‚àƒXƒYƒL‚ح‚ي‚½‚µ‚ج‘«‰؛‚ـ‚إ‚â‚ء‚ؤ
‚«‚ؤپu’ق‚è‚ ‚°‚ؤ‚ف‚وپv‚ئ’›”‚·‚éپB‚ي‚½‚µ‚ح‚¢‚آ‚à‚»‚ج’›”‚ةڈو
‚èپAڈں‚ء‚½ژژ‚µ‚ھ‚ب‚¢پBŒب‚جژp‚ًٹش‹ك‚ةŒ©‚¹‚éگ¶•¨پA‚»‚ê‚ھ’±‚إ‚
‚êپA–I‚إ‚ ‚êپA‹›‚إ‚ ‚êپA”ق‚ç‚ح‚»‚ê‚ب‚è‚ةŒx‰ْ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾پB‚»‚ê
‚ًڈم‰ٌ‚é‹Z—ت‚à’mŒb‚à‚ي‚½‚µ‚ة‚ح‚ب‚¢پBٹô“xچ•گ¯‚ًڈd‚ث‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚à‚³
‚ç‚ةڈd‚ث‚é‚ئ‚µ‚ؤ‚à–³ˆس–،‚³‚ًٹ´‚¶‚¸پA‚ـ‚¦‚ة‚à‘‚µ‚ؤ‚ي‚½‚µ‚جگS‚ح
چ‚‚ش‚é‚خ‚©‚肾پB
‚ھٹC–ت‚ة—V‚ر‚ةڈo‚é‚ج‚ً‘ز‚؟چ\‚¦‚½‚و‚¤‚ةپA”w•h‚ھ“ف‚¢‰¹‚ً‹؟‚©‚¹ٹC
–ت‚إ‚®‚é‚è‚ئˆê“]‚µپA‚ذ‚ئ“غ‚ف‚·‚éپBڈ¬‚³‚بˆ£‚µ‚ف‚ج—ض‚ھ’ç–h‚جچغ‚ـ
‚إٹٌ‚¹‚ؤ‚‚éپBژ‚ة‚ح‘ه’_•s“G‚ة‚àƒXƒYƒL‚ح‚ي‚½‚µ‚ج‘«‰؛‚ـ‚إ‚â‚ء‚ؤ
‚«‚ؤپu’ق‚è‚ ‚°‚ؤ‚ف‚وپv‚ئ’›”‚·‚éپB‚ي‚½‚µ‚ح‚¢‚آ‚à‚»‚ج’›”‚ةڈو
‚èپAڈں‚ء‚½ژژ‚µ‚ھ‚ب‚¢پBŒب‚جژp‚ًٹش‹ك‚ةŒ©‚¹‚éگ¶•¨پA‚»‚ê‚ھ’±‚إ‚
‚êپA–I‚إ‚ ‚êپA‹›‚إ‚ ‚êپA”ق‚ç‚ح‚»‚ê‚ب‚è‚ةŒx‰ْ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾پB‚»‚ê
‚ًڈم‰ٌ‚é‹Z—ت‚à’mŒb‚à‚ي‚½‚µ‚ة‚ح‚ب‚¢پBٹô“xچ•گ¯‚ًڈd‚ث‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚à‚³
‚ç‚ةڈd‚ث‚é‚ئ‚µ‚ؤ‚à–³ˆس–،‚³‚ًٹ´‚¶‚¸پA‚ـ‚¦‚ة‚à‘‚µ‚ؤ‚ي‚½‚µ‚جگS‚ح
چ‚‚ش‚é‚خ‚©‚肾پB
پ@’ھ‚ھˆّ‚‚ج‚ح–‚؟‚ؤ‚‚é‚ئ‚«‚و‚èپA‘¬‚¢‚و‚¤‚ةژv‚ي‚ê‚éپB–‚؟‚ؤ‚
‚é‚ئ‚«‚حٹC’ê‚ج‚و‚¤‚·‚ھŒ©‚¦‚ب‚‚ب‚é‚خ‚©‚è‚إپAˆّ‚«’ھ‚حڈ‚µ‚¸‚آ‘S
‘ج‚ھ–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚‚é‚©‚çپA‚ب‚¨‚³‚çˆّ‚«’ھ‚ة‚ح‰ء‘¬‚ھ‚©‚©‚ء‚ؤ‚¢
‚é‚و‚¤‚ةژv‚¦‚éپB
‚é‚ئ‚«‚حٹC’ê‚ج‚و‚¤‚·‚ھŒ©‚¦‚ب‚‚ب‚é‚خ‚©‚è‚إپAˆّ‚«’ھ‚حڈ‚µ‚¸‚آ‘S
‘ج‚ھ–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚‚é‚©‚çپA‚ب‚¨‚³‚çˆّ‚«’ھ‚ة‚ح‰ء‘¬‚ھ‚©‚©‚ء‚ؤ‚¢
‚é‚و‚¤‚ةژv‚¦‚éپB
پ@‚·‚إ‚ةƒXƒYƒL‚ج’§گي‚جڈê‚حٹ±ڈم‚ھ‚èپA‚³‚ء‚د‚è’ق‚è‚ح‚إ‚«‚ب‚‚ب
‚éپBƒxپ[ƒ‹‚ة•ï‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚½ٹC’ê‚ج‚و‚¤‚·‚ھ”»–¾‚·‚邱‚ئ‚ح‹»‚´‚ك‚إ‚à
‚ ‚éپB
‚éپBƒxپ[ƒ‹‚ة•ï‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚½ٹC’ê‚ج‚و‚¤‚·‚ھ”»–¾‚·‚邱‚ئ‚ح‹»‚´‚ك‚إ‚à
‚ ‚éپB
پ@گS“–‚½‚è‚جگ[‚فƒ|ƒCƒ“ƒg‚ةژش‚ً‘–‚点‚é‚©پAچ،–é‚ح“X‚¶‚ـ‚¢‚ئ‚·‚é
‚©پB‚¢‚¸‚ê‚ً‘I‘ً‚·‚é‚©پA‘پ‹}‚ب”»’f‚ً”—‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
‚©پB‚¢‚¸‚ê‚ً‘I‘ً‚·‚é‚©پA‘پ‹}‚ب”»’f‚ً”—‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
’ق‚ê‚ب‚¢“ْ
’ق‚èگl‚حŒ¾‚¢–َ‚ھچD‚«‚إ‚ ‚éپB‚»‚µ‚ؤ’ق‚è‚ة‚حŒ¾‚¢–َ‚ة‚±‚ئŒ‡‚©‚ب
‚¢چق—؟‚ھ‚½‚ٌ‚ئ‚ ‚éپBپu’ھ‚ھˆ«‚©‚ء‚½پvپu•—‚ھگپ‚¢‚ؤ‚ثپv‚ب‚ٌ‚ؤ‚ج‚ح
ڈک‚جŒû‚إپAژ‚ة‚حپu‹›‚ھ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پv‚ئٹC’ê‚ً”`‚«چ‚ٌ‚إ—ˆ‚½‚©‚ج‚و
‚¤‚ةŒ¾‚¤پBژ©‘R‚ھ‘ٹژè‚إ‚ ‚é‚©‚牽‚ئ‚إ‚àŒ¾‚¦‚éپB‚»‚ê‚ھژ©‚ç‚ًˆش
‚كپAژں‚جٹˆ—ح‚ة‚ب‚éپB
‚¢چق—؟‚ھ‚½‚ٌ‚ئ‚ ‚éپBپu’ھ‚ھˆ«‚©‚ء‚½پvپu•—‚ھگپ‚¢‚ؤ‚ثپv‚ب‚ٌ‚ؤ‚ج‚ح
ڈک‚جŒû‚إپAژ‚ة‚حپu‹›‚ھ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پv‚ئٹC’ê‚ً”`‚«چ‚ٌ‚إ—ˆ‚½‚©‚ج‚و
‚¤‚ةŒ¾‚¤پBژ©‘R‚ھ‘ٹژè‚إ‚ ‚é‚©‚牽‚ئ‚إ‚àŒ¾‚¦‚éپB‚»‚ê‚ھژ©‚ç‚ًˆش
‚كپAژں‚جٹˆ—ح‚ة‚ب‚éپB
پ@’ق‚èگl‚حژv‚¤پBٹC‚ج’ê‚ً”`‚¢‚ؤ‚ف‚½‚¢‚à‚ج‚¾‚ئپBژ©•ھ‚ج‰a‚جژü‚è‚ة
‚ح‚ا‚ٌ‚ب‹›‚ھٹٌ‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA‰½‚ًچl‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚낤‚©‚ئپB‘پ‚‚د‚‚è
‚ئ‚â‚ء‚ؤ‚‚ê‚و‚ئپB
‚ح‚ا‚ٌ‚ب‹›‚ھٹٌ‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA‰½‚ًچl‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚낤‚©‚ئپB‘پ‚‚د‚‚è
‚ئ‚â‚ء‚ؤ‚‚ê‚و‚ئپB
پ@’ق‚èگl‚حچl‚¦‚éپB’ق‚ê‚é‚ئ•·‚¢‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚ةˆêŒü‚ة’ق‚ê‚ب‚¢‚¶‚ل‚ب‚¢
‚©پB‚؟‚ه‚ء‚ئ‚خ‚©‚èڈêڈٹ‚ھˆل‚¤‚ج‚©‚بپB•‚‚«‰؛‚حچ‡‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚낤
‚©پB‚¢‚â‚¢‚â‰a‚ح‚â‚ء‚د‚èƒAƒŒ‚ھ‚و‚©‚ء‚½‚ج‚¾پB‚»‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àپA’ق‚ê
‚é“ْ‚ئ’ق‚ê‚ب‚¢“ْ‚ھ‘O‚à‚ء‚ؤ•ھ‚©‚ê‚خ‚ب‚ پA‚ئپB‚»‚¤‚â‚ء‚ؤ’Z‚¢‹x“ْ
‚ھٹC‚ج‘O‚إڈI‚éپB
‚©پB‚؟‚ه‚ء‚ئ‚خ‚©‚èڈêڈٹ‚ھˆل‚¤‚ج‚©‚بپB•‚‚«‰؛‚حچ‡‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚낤
‚©پB‚¢‚â‚¢‚â‰a‚ح‚â‚ء‚د‚èƒAƒŒ‚ھ‚و‚©‚ء‚½‚ج‚¾پB‚»‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àپA’ق‚ê
‚é“ْ‚ئ’ق‚ê‚ب‚¢“ْ‚ھ‘O‚à‚ء‚ؤ•ھ‚©‚ê‚خ‚ب‚ پA‚ئپB‚»‚¤‚â‚ء‚ؤ’Z‚¢‹x“ْ
‚ھٹC‚ج‘O‚إڈI‚éپB
پ@‚ ‚ پ[پA‹Cژ‚؟‚و‚©‚ء‚½‚ب‚ پB’ق‚ê‚ب‚‚ؤ‚à‚±‚¤‚â‚ء‚ؤˆê“ْ‚ً‰ك‚²
‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ؤƒzƒ“ƒgپA‚و‚©‚ء‚½پB
‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ؤƒzƒ“ƒgپA‚و‚©‚ء‚½پB
‹AکHپB’ق‚èگl‚ح‚ـ‚½چl‚¦‚éپB’ق‚ê‚é“ْ‚ئ’ق‚ê‚ب‚¢“ْ‚ھ‘O‚à‚ء‚ؤ•ھ‚©
‚ê‚خ‚ب‚ پA‚ئپB
‚ê‚خ‚ب‚ پA‚ئپB

پ@”é–§‰ï’k
پ@’ç–h‚إ’ق‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئپA‚³‚ي‚³‚ي‚ئ‰H‰¹‚ً‚½‚ؤ‚ؤپA’ك‚ھˆê‰H•‘‚¢چ~‚è
‚ؤ—ˆ‚½پB‚ي‚½‚µ‚©‚çگ”•à‚à—£‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢ڈٹ‚ة“ث‚ء—§‚ء‚ؤپA‚ي‚½‚µ‚جƒE
ƒL‚ً’‚ك‚ؤ‚¢‚éپB
‚ؤ—ˆ‚½پB‚ي‚½‚µ‚©‚çگ”•à‚à—£‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢ڈٹ‚ة“ث‚ء—§‚ء‚ؤپA‚ي‚½‚µ‚جƒE
ƒL‚ً’‚ك‚ؤ‚¢‚éپB
پ@‚ـ‚¾ŒF–{‚إ‹خ–±‚µ‚ؤ‚¢‚½‚±‚ëپA‚â‚ح‚è–é’ق‚è‚إپA‚â‚ء‚ئ’ق‚èڈم‚°‚½
ڈ¶‚ظ‚ا‚جƒNƒچƒ_ƒC‚ًٹئگو‚©‚ç’n–ت‚ةچ~‚낵‚½‚ئ‚½‚ٌپAگِ‚ٌ‚إ‚¢‚½–ى—ا
”L‚ة‰،ژو‚肳‚ꂽ‚±‚ئ‚ھ‚ ‚ء‚½پB‹›‚ة‚ح‚ـ‚¾گj‚ئژ…‚ھ•t‚¢‚ؤ‚¢‚ؤپAçً
‚¦‚ؤ‘–‚ء‚½‚ئ‚½‚ٌپA‚ي‚½‚µ‚ح–hŒن“I‚ةٹئ‚ًˆّ‚ء’£‚ء‚½‚ج‚إ–ى—ا”L‚حپA
ƒ€ƒMƒ…پA‚ئŒ™‚إ‚à‚ي‚½‚µ‚ةٹç‚ًŒü‚¯‚½پB‚¨‚»‚ç‚‚»‚جژپA–ى—ا”L‚حڈ‰
‚ك‚ؤ‚»‚ج‹›‚ھ“V‚جŒb‚ف‚إچ~‚ء‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA‚«‚؟‚ٌ‚ئژ‚؟ژه‚ج‚
‚é—Rڈڈگ³‚µ‚¢‹›‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ة‹C•t‚¢‚½‚ح‚¸‚¾پB‚µ‚©‚µ‚»‚ج”L‚ھ•پ’ت‚ج
”L‚ئˆل‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚±‚ë‚حپA‚»‚ê‚إ‚à‚ب‚¨پAٹl•¨‚ًژè•ْ‚³‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤چھ
گ«‚جژ‚؟ژه‚إ‚ ‚ء‚½‚±‚ئ‚¾پB‚³‚ç‚ة‹ء‚‚ׂ«‚±‚ئ‚ة‚حپA‹›‚جŒû‚©‚çڈu
‚ٹش‚ةگj‚ًڈمژè‚ةٹO‚·‚ئ‚¢‚¤’mŒb‚ـ‚إ”ُ‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚¾پB‚â
‚ء‚ئ‚ج’ق‰ت‚ً‰،ژو‚肳‚ꂽ‰÷‚µ‚³‚و‚èپA‚ ‚ج‚و‚¤‚ة—D‚ꂽ”L‚ھ‰B“ظ‚ج
گ¶ٹˆ‚ً‘—‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤Œûگة‚µ‚³پA‚»‚ê‚ح‚ب‚؛‚©‚·‚ھ‚·‚ھ‚µ‚¢‹C•ھ‚ة
•د‰»‚µ‚ؤپA‚¢‚آ‚ـ‚إ‚à‚±‚±‚ë‚ةژc‚ء‚½پB
ڈ¶‚ظ‚ا‚جƒNƒچƒ_ƒC‚ًٹئگو‚©‚ç’n–ت‚ةچ~‚낵‚½‚ئ‚½‚ٌپAگِ‚ٌ‚إ‚¢‚½–ى—ا
”L‚ة‰،ژو‚肳‚ꂽ‚±‚ئ‚ھ‚ ‚ء‚½پB‹›‚ة‚ح‚ـ‚¾گj‚ئژ…‚ھ•t‚¢‚ؤ‚¢‚ؤپAçً
‚¦‚ؤ‘–‚ء‚½‚ئ‚½‚ٌپA‚ي‚½‚µ‚ح–hŒن“I‚ةٹئ‚ًˆّ‚ء’£‚ء‚½‚ج‚إ–ى—ا”L‚حپA
ƒ€ƒMƒ…پA‚ئŒ™‚إ‚à‚ي‚½‚µ‚ةٹç‚ًŒü‚¯‚½پB‚¨‚»‚ç‚‚»‚جژپA–ى—ا”L‚حڈ‰
‚ك‚ؤ‚»‚ج‹›‚ھ“V‚جŒb‚ف‚إچ~‚ء‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA‚«‚؟‚ٌ‚ئژ‚؟ژه‚ج‚
‚é—Rڈڈگ³‚µ‚¢‹›‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ة‹C•t‚¢‚½‚ح‚¸‚¾پB‚µ‚©‚µ‚»‚ج”L‚ھ•پ’ت‚ج
”L‚ئˆل‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚±‚ë‚حپA‚»‚ê‚إ‚à‚ب‚¨پAٹl•¨‚ًژè•ْ‚³‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤چھ
گ«‚جژ‚؟ژه‚إ‚ ‚ء‚½‚±‚ئ‚¾پB‚³‚ç‚ة‹ء‚‚ׂ«‚±‚ئ‚ة‚حپA‹›‚جŒû‚©‚çڈu
‚ٹش‚ةگj‚ًڈمژè‚ةٹO‚·‚ئ‚¢‚¤’mŒb‚ـ‚إ”ُ‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚¾پB‚â
‚ء‚ئ‚ج’ق‰ت‚ً‰،ژو‚肳‚ꂽ‰÷‚µ‚³‚و‚èپA‚ ‚ج‚و‚¤‚ة—D‚ꂽ”L‚ھ‰B“ظ‚ج
گ¶ٹˆ‚ً‘—‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤Œûگة‚µ‚³پA‚»‚ê‚ح‚ب‚؛‚©‚·‚ھ‚·‚ھ‚µ‚¢‹C•ھ‚ة
•د‰»‚µ‚ؤپA‚¢‚آ‚ـ‚إ‚à‚±‚±‚ë‚ةژc‚ء‚½پB
پ@’ك‚à‚â‚ح‚è‚ي‚½‚µ‚ج‹›‚ً‘_‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚낤‚©پBگj‚ًٹO‚·‹Z”\‚ً‚à
ژ‚؟چ‡‚ي‚¹‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚낤‚©پB‚ي‚½‚µ‚حپuƒtƒBƒCپAƒtƒBƒCپv‚ئگO‚ًگë
‚点‚ؤ’ك‚ةچ‡گ}‚ً‘—‚è‚ب‚ھ‚çپA’ك‚ئ‚ج‹——£‚ً‚¢‚ء‚»‚¤ڈk‚ك‚½پB‹C–،ˆ«
‚ھ‚ء‚ؤ‚à‚¤‚ذ‚ئ‚آ‰«‚ج’ç–h‚ة”ٍ‚ٌ‚إچs‚ء‚ؤ‚‚ê‚é‚à‚و‚µپAگaژm‹¦’è‚ً
Œ‹‚ٌ‚إپAگl‚ج•¨‚ة‚حژè‚ًڈo‚³‚ب‚¢‚±‚ئ‚ة‚µ‚ؤ‚‚ê‚ê‚خپAˆêڈڈ‚ةƒEƒL‚ً
’‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚ه‚¤پBƒEƒL‚ھ’¾‚ٌ‚إ‚à‚»‚ê‚ح‚ ‚ب‚½‚ة‚حٹضŒW‚ج‚ب‚¢‚±‚ئ
‚إ‚ ‚ء‚ؤپA‹›‚ھٹ|‚ء‚ؤ‚àٹ|‚ç‚ب‚‚ؤ‚àپA‚ ‚ب‚½‚حٹى‚شگl‚إ‚ح‚ب‚پA‚ي
‚½‚µ‚ًگ^ژ—‚ؤ—ژ’_‚·‚é•K—v‚à‚ب‚¢پB‰½ژٹش‚إ‚à‚»‚±‚ة“ث‚ء—§‚ء‚ؤ‚¢‚é
‚ج‚ح‚ ‚ب‚½‚جژ©—R‚إ‚ ‚é‚ھپA• ‚ھŒ¸‚ء‚½‚çپAژ©”“I‚ة‚ا‚±‚©‚ضˆع‚ء‚ؤ
‚‚êپB‚»‚ê‚©‚ç‚بپA‚»‚ٌ‚ب‚ةŒ©‘¹‚ب‚ء‚½ٹلچ·‚µ‚ً‚ي‚½‚µ‚ةŒü‚¯‚ب‚¢‚إ
‚‚êپBٹل‚ًˆح‚ٌ‚¾چ•گF‚ج‰H–ر‚ھˆê’i‚ئٹل‚ً‰s‚Œ©‚¹‚éپB
ژ‚؟چ‡‚ي‚¹‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚낤‚©پB‚ي‚½‚µ‚حپuƒtƒBƒCپAƒtƒBƒCپv‚ئگO‚ًگë
‚点‚ؤ’ك‚ةچ‡گ}‚ً‘—‚è‚ب‚ھ‚çپA’ك‚ئ‚ج‹——£‚ً‚¢‚ء‚»‚¤ڈk‚ك‚½پB‹C–،ˆ«
‚ھ‚ء‚ؤ‚à‚¤‚ذ‚ئ‚آ‰«‚ج’ç–h‚ة”ٍ‚ٌ‚إچs‚ء‚ؤ‚‚ê‚é‚à‚و‚µپAگaژm‹¦’è‚ً
Œ‹‚ٌ‚إپAگl‚ج•¨‚ة‚حژè‚ًڈo‚³‚ب‚¢‚±‚ئ‚ة‚µ‚ؤ‚‚ê‚ê‚خپAˆêڈڈ‚ةƒEƒL‚ً
’‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚ه‚¤پBƒEƒL‚ھ’¾‚ٌ‚إ‚à‚»‚ê‚ح‚ ‚ب‚½‚ة‚حٹضŒW‚ج‚ب‚¢‚±‚ئ
‚إ‚ ‚ء‚ؤپA‹›‚ھٹ|‚ء‚ؤ‚àٹ|‚ç‚ب‚‚ؤ‚àپA‚ ‚ب‚½‚حٹى‚شگl‚إ‚ح‚ب‚پA‚ي
‚½‚µ‚ًگ^ژ—‚ؤ—ژ’_‚·‚é•K—v‚à‚ب‚¢پB‰½ژٹش‚إ‚à‚»‚±‚ة“ث‚ء—§‚ء‚ؤ‚¢‚é
‚ج‚ح‚ ‚ب‚½‚جژ©—R‚إ‚ ‚é‚ھپA• ‚ھŒ¸‚ء‚½‚çپAژ©”“I‚ة‚ا‚±‚©‚ضˆع‚ء‚ؤ
‚‚êپB‚»‚ê‚©‚ç‚بپA‚»‚ٌ‚ب‚ةŒ©‘¹‚ب‚ء‚½ٹلچ·‚µ‚ً‚ي‚½‚µ‚ةŒü‚¯‚ب‚¢‚إ
‚‚êپBٹل‚ًˆح‚ٌ‚¾چ•گF‚ج‰H–ر‚ھˆê’i‚ئٹل‚ً‰s‚Œ©‚¹‚éپB
پ@‚ي‚½‚µ‚ح–é’ق‚è‚إ‚ح‚¢‚آ‚àگآƒPƒu‚ئ‚¢‚¤ƒ~ƒ~ƒY‚ةژ—‚½‰a‚ًژg‚¤‚ج‚¾
‚ھپA‚ا‚¤‚¢‚¤’ژ‚ج’m‚点‚©پA‚»‚ج“ْ‚ح—â“€ƒGƒr‚ًژ‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ‚¢‚½پB‚»
‚ê‚à‘ٍژRژ‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚±‚إŒ^‚ج•ِ‚ꂽڈ¬‚³‚بƒGƒr‚ً‘I‚èپA’ك‚ج‘«‰؛
‚ة•ْ‚ء‚ؤ‚ف‚½پB”g‚ج‰¹‚à•—‚ج‰¹‚à‚ب‚¢–ب–ر‚ج‚و‚¤‚بˆإ‚ة‚ب‚©‚ةپA‚ظ‚ئ
‚èپA‚ئ‹َ‹C‚ھگU“®‚µپA’ك‚جڑ{‚ھپA‚ز‚ءپA‚ئ’n–ت‚ًŒü‚¢‚½پB‚»‚µ‚ؤ“إ“ü
‚è‚ئ‚àگj•t‚«‚ئ‚à‚ـ‚ء‚½‚‹^‚¤‚±‚ئ‚ب‚پA‚ذ‚ئ“ث‚«‚إگH‚ׂ½پBپ@پ@‚ي
‚½‚µ‚حٹô“x‚©“ٹ‚°‚â‚ء‚½پB’ك‚ة‚àƒvƒ‰ƒCƒh‚ھ‚ ‚é‚炵‚پA‚»‚ج‚½‚ر‚ة
–ہکf‚»‚¤‚بژ‹گü‚ً‚ي‚½‚µ‚ة‚‚ê‚ؤپA‚µ‚©‚µپuگeگط‚حژَ‚¯‚é‚يپv‚ب‚ٌ‚ؤ
ŒJ‚è•ش‚µ‚ب‚ھ‚çپA‚ذ‚ئ“غ‚ف‚¾‚ء‚½پB‹ةڈم‚ج–éگH‚ة‚ ‚â‚©‚ء‚ؤپA“àگS‚ظ
‚‚ظ‚‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ح‚ي‚©‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
‚ھپA‚ا‚¤‚¢‚¤’ژ‚ج’m‚点‚©پA‚»‚ج“ْ‚ح—â“€ƒGƒr‚ًژ‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ‚¢‚½پB‚»
‚ê‚à‘ٍژRژ‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚±‚إŒ^‚ج•ِ‚ꂽڈ¬‚³‚بƒGƒr‚ً‘I‚èپA’ك‚ج‘«‰؛
‚ة•ْ‚ء‚ؤ‚ف‚½پB”g‚ج‰¹‚à•—‚ج‰¹‚à‚ب‚¢–ب–ر‚ج‚و‚¤‚بˆإ‚ة‚ب‚©‚ةپA‚ظ‚ئ
‚èپA‚ئ‹َ‹C‚ھگU“®‚µپA’ك‚جڑ{‚ھپA‚ز‚ءپA‚ئ’n–ت‚ًŒü‚¢‚½پB‚»‚µ‚ؤ“إ“ü
‚è‚ئ‚àگj•t‚«‚ئ‚à‚ـ‚ء‚½‚‹^‚¤‚±‚ئ‚ب‚پA‚ذ‚ئ“ث‚«‚إگH‚ׂ½پBپ@پ@‚ي
‚½‚µ‚حٹô“x‚©“ٹ‚°‚â‚ء‚½پB’ك‚ة‚àƒvƒ‰ƒCƒh‚ھ‚ ‚é‚炵‚پA‚»‚ج‚½‚ر‚ة
–ہکf‚»‚¤‚بژ‹گü‚ً‚ي‚½‚µ‚ة‚‚ê‚ؤپA‚µ‚©‚µپuگeگط‚حژَ‚¯‚é‚يپv‚ب‚ٌ‚ؤ
ŒJ‚è•ش‚µ‚ب‚ھ‚çپA‚ذ‚ئ“غ‚ف‚¾‚ء‚½پB‹ةڈم‚ج–éگH‚ة‚ ‚â‚©‚ء‚ؤپA“àگS‚ظ
‚‚ظ‚‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ح‚ي‚©‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
پ@‘جگF‚حƒiƒxƒdƒ‹‚»‚ء‚‚è‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپA‚»‚ê‚حڈ‚µ”w‚ج’ل‚¢پAژٌ‚à‹r
‚à‚¢‚•ھ’Z‚ك‚جƒAƒIƒTƒM‚ئژv‚ي‚ꂽپB‚ب‚ٌ‚ئگlٹµ‚ꂵ‚½ƒAƒIƒTƒM‚إ‚
‚邱‚ئ‚©پB‚ ‚é‚¢‚ح‚±‚ج’¹‚¾‚¯“ء•تٹج‚جگک‚ي‚ء‚½’¹‚ب‚ج‚©پB
‚à‚¢‚•ھ’Z‚ك‚جƒAƒIƒTƒM‚ئژv‚ي‚ꂽپB‚ب‚ٌ‚ئگlٹµ‚ꂵ‚½ƒAƒIƒTƒM‚إ‚
‚邱‚ئ‚©پB‚ ‚é‚¢‚ح‚±‚ج’¹‚¾‚¯“ء•تٹج‚جگک‚ي‚ء‚½’¹‚ب‚ج‚©پB
پ@‚ي‚½‚µ‚ئƒAƒIƒTƒM‚ح‚ز‚‚è‚ئ‚à‚µ‚ب‚¢ƒEƒL‚ً‰«‚ض‰«‚ض•Y‚ي‚¹‚ب‚ھ‚ç
ˆêژٹش‚ظ‚اپA’·‚—₽‚¢’N‚à‚¢‚ب‚¢’ç–h‚جڈم‚إ‰ك‚²‚µ‚½پBکb‚µ‚à‘ٍژR
‚µ‚½پB
ˆêژٹش‚ظ‚اپA’·‚—₽‚¢’N‚à‚¢‚ب‚¢’ç–h‚جڈم‚إ‰ك‚²‚µ‚½پBکb‚µ‚à‘ٍژR
‚µ‚½پB
پ@‚ا‚ٌ‚بکb‚µ‚ً‚µ‚½‚©‚حپAƒAƒIƒTƒM‚ئ‚ج–ٌ‘©‚إپA”é–§‚ة‚µ‚ؤ‚¨‚©‚ث‚خ
‚ب‚ç‚ب‚¢پB
‚ب‚ç‚ب‚¢پB
 پ@ژتگ^پGhttp://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%82%B5%
پ@ژتگ^پGhttp://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%82%B5%E3%82%AE&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=پ@‚و‚è
‘S’·88-98cmپB—ƒٹJ’£150-170cmپB‘جڈd1.2-1.8kgپBڈم–ت‚حگآ‚ف‚ھ‚©‚ء‚½ٹDگF‚ج‰H–ر‚إ”ي‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
ƒAƒIƒTƒM‚حپAƒAƒtƒٹƒJ‘ه—¤پAƒ†پ[ƒ‰ƒVƒA‘ه—¤پAƒCƒMƒٹƒXپAƒCƒ“ƒhƒlƒVƒAگ¼•”پA“ْ–{پAƒtƒBƒٹƒsƒ“–k
•”پAƒ}ƒ_ƒKƒXƒJƒ‹‚ة•ھ•z‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‰ؤ‹G‚ةƒ†پ[ƒ‰ƒVƒA‘ه—¤’†ˆـ“x’n•û‚إ”ةگB‚µپA“~‹G‚ة‚ب‚é‚ئƒAƒt
ƒٹƒJ‘ه—¤’†•”پA“Œ“ىƒAƒWƒA‚ب‚ا‚ض“ى‰؛‚µ‰z“~‚·‚éپBƒAƒtƒٹƒJ‘ه—¤“ى•”‚⃆پ[ƒ‰ƒVƒA‘ه—¤“ى•”‚ب‚ا‚إ
‚حژü”Nگ¶‘§‚·‚éپB“ْ–{‚إ‚حˆںژيƒAƒIƒTƒM‚ھ‰ؤ‹G‚ة–kٹC“¹‚إ”ةگB‚µپi‰ؤ’¹پjپA“~‹G‚ة‹مڈBˆب“ى‚ة‰z“~
‚ج‚½‚ك”ٍ—ˆ‚·‚éپi“~’¹پjپB–{ڈBپAژlچ‘‚إ‚حژü”Nگ¶‘§‚·‚éپi—¯’¹پjپBپپhttp://ja.wikipedia.org/
wiki/%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%82%B5%E3%82%AEپG³¨·حكأق±پEƒtƒٹپ|•S‰بژ–“T‚و‚è
ƒAƒIƒTƒM‚حپAƒAƒtƒٹƒJ‘ه—¤پAƒ†پ[ƒ‰ƒVƒA‘ه—¤پAƒCƒMƒٹƒXپAƒCƒ“ƒhƒlƒVƒAگ¼•”پA“ْ–{پAƒtƒBƒٹƒsƒ“–k
•”پAƒ}ƒ_ƒKƒXƒJƒ‹‚ة•ھ•z‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‰ؤ‹G‚ةƒ†پ[ƒ‰ƒVƒA‘ه—¤’†ˆـ“x’n•û‚إ”ةگB‚µپA“~‹G‚ة‚ب‚é‚ئƒAƒt
ƒٹƒJ‘ه—¤’†•”پA“Œ“ىƒAƒWƒA‚ب‚ا‚ض“ى‰؛‚µ‰z“~‚·‚éپBƒAƒtƒٹƒJ‘ه—¤“ى•”‚⃆پ[ƒ‰ƒVƒA‘ه—¤“ى•”‚ب‚ا‚إ
‚حژü”Nگ¶‘§‚·‚éپB“ْ–{‚إ‚حˆںژيƒAƒIƒTƒM‚ھ‰ؤ‹G‚ة–kٹC“¹‚إ”ةگB‚µپi‰ؤ’¹پjپA“~‹G‚ة‹مڈBˆب“ى‚ة‰z“~
‚ج‚½‚ك”ٍ—ˆ‚·‚éپi“~’¹پjپB–{ڈBپAژlچ‘‚إ‚حژü”Nگ¶‘§‚·‚éپi—¯’¹پjپBپپhttp://ja.wikipedia.org/
wiki/%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%82%B5%E3%82%AEپG³¨·حكأق±پEƒtƒٹپ|•S‰بژ–“T‚و‚è
پ@‘û‚ج‘«
پ@—§ڈt‚ً‰ك‚¬‚ؤ’g‚©‚¢“ْ‚ھ‘±‚¢‚½پB‹ڈ‚ؤ‚à—§‚ء‚ؤ‚à‚¨‚ê‚ب‚¢‚و‚¤‚·‚إ’ق‚è—F
‚ج‚l‚³‚ٌ‚©‚ç“dکb‚ھ“ü‚ء‚½پB
‚ج‚l‚³‚ٌ‚©‚ç“dکb‚ھ“ü‚ء‚½پB
پu‚à‚¤‚¢‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚¢‚آچs‚«‚ـ‚·پHپv
پuٹC‚ج‚ب‚©‚ح‚ـ‚¾گ^“~‚إ‚·‚وپB‚إ‚àچs‚ء‚ؤ‚ف‚ـ‚·‚©پv
ژٹْ‘پپX‚ئ‚حژv‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚ي‚½‚µ‚à‚¤‚¸‚¤‚¸‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚±‚낾پB‹Cچ‡‚¢‚ً“ü
‚ê‚ؤ–¾’©8ژ‚ةچ`‚إ‘زچ‡‚ي‚¹‚ً‚·‚éپB‚ي‚½‚µ‚ح6ژپA‚l‚³‚ٌ‚ح5ژ‰ك‚¬‚ة‚ح
‹Nڈ°‚¹‚ث‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚ھپA‹C‰·‚ھڈ‚µڈم‚ھ‚ء‚½‚±‚ئ‚إگh‚³‚حٹ´‚¶‚ب‚¢پB
‚ê‚ؤ–¾’©8ژ‚ةچ`‚إ‘زچ‡‚ي‚¹‚ً‚·‚éپB‚ي‚½‚µ‚ح6ژپA‚l‚³‚ٌ‚ح5ژ‰ك‚¬‚ة‚ح
‹Nڈ°‚¹‚ث‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚ھپA‹C‰·‚ھڈ‚µڈم‚ھ‚ء‚½‚±‚ئ‚إگh‚³‚حٹ´‚¶‚ب‚¢پB
پ@’ق‰ت‚حڈW‚ـ‚ء‚½‚ا‚ج‘D‚àژv‚ي‚µ‚‚ب‚پAˆê“ْ‚©‚¯‚ؤ‚ي‚½‚µ‚à‚l‚³‚ٌ‚àƒAƒW2
•C‚¾‚ء‚½‚ھپA‚©‚ê‚ح‘ه‘û‚ً’ق‚è‚ ‚°‚ؤ‚¢‚½پB
•C‚¾‚ء‚½‚ھپA‚©‚ê‚ح‘ه‘û‚ً’ق‚è‚ ‚°‚ؤ‚¢‚½پB
پu”¼•ھ‚ ‚°‚é‚وپv
‘ه‘û‚¾‚¯‚ةٹً‚µ‚¢پB
پu‚¶‚ل‚ پA‚ي‚½‚µ‚جƒAƒWپA‚ ‚°‚ـ‚·‚وپv
‚ي‚½‚µ‚ح‹z‚¢•t‚¢‚ؤ’ïچR‚µ‚ؤ—ˆ‚é‘û‚ج“ھ‚ً— •ش‚µ‚ة‚µپA“à‘ں‚ًژو‚èڈœ‚«پA‘«
‚ً4–{‚ئ4–{چ¶‰E‚ة•ھ‚¯پA‚»‚±‚©‚çگ^‚ء“ٌ‚آ‚ةگط‚èژو‚ء‚½پB
‚ً4–{‚ئ4–{چ¶‰E‚ة•ھ‚¯پA‚»‚±‚©‚çگ^‚ء“ٌ‚آ‚ةگط‚èژو‚ء‚½پB
پ@‘û‚ح‰–‚à‚ف‚إ‚ت‚ك‚è‚ًڈœ‚¢‚½‚ ‚ئŒy‚ن¥‚إ‚ؤ”¼گ¶‚ج‘ûژh‚µ‚ھ”سژق‚ةچإچ‚
‚¾پB‚±‚ٌ‚ب‚ة‘ه‚«‚¢‚ئ‘«2–{‚إڈ\•ھ‚¾پBژc‚è‚ح—â“€‚µ‚ؤ‚¨‚¯‚خ”¼”N‚إ‚à1”NŒo
‚ء‚ؤ‚àƒ^ƒRڈؤ‚«‚إ‚àƒ`ƒƒƒ“ƒ|ƒ“‚ج‹ïچق‚إ‚àژg‚¦‚éپB•غ‘¶گ«‚ھ‚¢‚¢‚ج‚à‘û‚ً’ق
‚ء‚½‚ئ‚«‚جٹى‚ر‚ج‚ذ‚ئ‚آ‚¾پB
‚¾پB‚±‚ٌ‚ب‚ة‘ه‚«‚¢‚ئ‘«2–{‚إڈ\•ھ‚¾پBژc‚è‚ح—â“€‚µ‚ؤ‚¨‚¯‚خ”¼”N‚إ‚à1”NŒo
‚ء‚ؤ‚àƒ^ƒRڈؤ‚«‚إ‚àƒ`ƒƒƒ“ƒ|ƒ“‚ج‹ïچق‚إ‚àژg‚¦‚éپB•غ‘¶گ«‚ھ‚¢‚¢‚ج‚à‘û‚ً’ق
‚ء‚½‚ئ‚«‚جٹى‚ر‚ج‚ذ‚ئ‚آ‚¾پB
پ@‹ك‚‚إ’ق‚ء‚ؤ‚¢‚é‘D‚©‚ç‰ïکb‚ھ•·‚±‚¦‚ؤ‚‚éپB’ق‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚«‚حٹ½گ؛‚خ‚©‚è
‚ھ•·‚±‚¦‚ؤ‚‚é‚ھپA’ق‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئ‚«‚ح‚ع‚â‚«‚جگ؛‚¾پB
‚ھ•·‚±‚¦‚ؤ‚‚é‚ھپA’ق‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئ‚«‚ح‚ع‚â‚«‚جگ؛‚¾پB
پu‹{چè‚إ‚حŒû’û‰u‚â‚ç’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU‚â‚ç‘ه•د‚â‚ھپA‹›‚¾‚¯‚حƒCƒ“ƒtƒ‹‚ب
‚ٌ‚ؤپA•·‚©‚ٌ‚ب‚ پB‹›‚ھˆê”ش•—ژׂذ‚«‚»‚¤‚â‚ھپB–ˆ“ْپA‰j‚¢‚إ‚ب‚ پv
‚ٌ‚ؤپA•·‚©‚ٌ‚ب‚ پB‹›‚ھˆê”ش•—ژׂذ‚«‚»‚¤‚â‚ھپB–ˆ“ْپA‰j‚¢‚إ‚ب‚ پv
‚¤‚ـ‚¢‚±‚ئŒ¾‚¤پB
پ@‹AکH‚à‰^“]‚µ‚ب‚ھ‚çپA‰½“x‚àژv‚¢ڈo‚µپA‚ذ‚ئ‚è‚ظ‚ظڈخ‚ٌ‚¾پB
پ@
پ@ژض‘«پGگ^‚ء“ٌ‚آ‚ة•ھ‚¯‚½‚ح‚¸‚ج‘û‚ج‘«پA‚ي‚½‚µ‚ج•û‚ح3–{‚¾‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@ˆبŒمپA‚±‚ج‚و‚¤‚بژ¸”s‚ح‹–‚³‚ê‚تپB

پ@ڈ‰’ق‚è
پ@„M‚³‚ٌ‚ئ’ق‚è‚ج–ٌ‘©‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½‚©‚çپAŒك‘O7ژ‚ة‚ز‚½‚è‚ئ–ع‚ھٹo‚ك‚½پBڈ‰’ق
‚è‚إ‚ ‚éپB“VŒَ‚ح—اچDپB•—‚ح‚ي‚¸‚©‚ة–ط‚ج—t‚ھ—h‚ê‚é’ِ“x‚إ‚ ‚éپB–ٌ‘©‚ج
ژٹش‚حچ`‚ة11ژ‚¾‚©‚çپA10ژ‚ً‰ك‚¬‚ؤژ©‘î‚ًڈo”‚·‚ê‚خٹش‚ةچ‡‚¤‚ج‚¾‚ھپA
”N––‚ةژ‚؟‹A‚ء‚ؤ‚¢‚½ٹئ‚ئƒٹپ[ƒ‹‚جژè“ü‚ê‚ھ‚إ‚«‚ؤ‚¢‚ب‚¢پBڈ¬•¨“ü‚ê‚جگ®
—‚à‚µ‚ؤ‚¨‚«‚½‚¢پBژg‚¢Œأ‚µ‚½ژ•ƒuƒ‰ƒV‚ةگ…‚ً‚©‚¯‚ب‚ھ‚çƒٹپ[ƒ‹‚ج‰ک‚ê‚ً—ژ
‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ
‚è‚إ‚ ‚éپB“VŒَ‚ح—اچDپB•—‚ح‚ي‚¸‚©‚ة–ط‚ج—t‚ھ—h‚ê‚é’ِ“x‚إ‚ ‚éپB–ٌ‘©‚ج
ژٹش‚حچ`‚ة11ژ‚¾‚©‚çپA10ژ‚ً‰ك‚¬‚ؤژ©‘î‚ًڈo”‚·‚ê‚خٹش‚ةچ‡‚¤‚ج‚¾‚ھپA
”N––‚ةژ‚؟‹A‚ء‚ؤ‚¢‚½ٹئ‚ئƒٹپ[ƒ‹‚جژè“ü‚ê‚ھ‚إ‚«‚ؤ‚¢‚ب‚¢پBڈ¬•¨“ü‚ê‚جگ®
—‚à‚µ‚ؤ‚¨‚«‚½‚¢پBژg‚¢Œأ‚µ‚½ژ•ƒuƒ‰ƒV‚ةگ…‚ً‚©‚¯‚ب‚ھ‚çƒٹپ[ƒ‹‚ج‰ک‚ê‚ً—ژ
‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ
پuچ،‚©‚çڈo‚éپBچ`‚ة‚ح10ژ‚±‚ë‚ة‚ح’…‚«‚ـ‚·پv
‚ئکA—چ‚ھ“ü‚éپBƒVƒiƒٹƒI‚ھ1ژٹش‹¶‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB“¹‹ï‚جژè“ü‚ê‚ح‚»‚±‚»‚±‚ة
’©گH‚ًچد‚ـ‚¹‚éپB•ظ“–‚ج‘م‚è‚ةƒoƒiƒi‚ً2–{پAƒoƒbƒO‚ة“ث‚ءچ‚ٌ‚¾پB
’©گH‚ًچد‚ـ‚¹‚éپB•ظ“–‚ج‘م‚è‚ةƒoƒiƒi‚ً2–{پAƒoƒbƒO‚ة“ث‚ءچ‚ٌ‚¾پB
پ@چ`‚ة’…‚‚ئŒW—¯‚µ‚ؤ‚¢‚é‘D‚ة‚ح–kگ¼‚ج‹‚¢•—‚ھ“–‚½‚èپAŒƒ‚µ‚ƒچپ[ƒٹƒ“ƒO‚µ
‚ؤ‚¢‚éپB’ç–h‚©‚çŒü‚±‚¤‚ح”’”g‚ھ—§‚ء‚ؤپA‚ئ‚ؤ‚àڈoچ`‚إ‚«‚éڈَ‘ش‚إ‚ح‚ب‚¢پB
‚ؤ‚¢‚éپB’ç–h‚©‚çŒü‚±‚¤‚ح”’”g‚ھ—§‚ء‚ؤپA‚ئ‚ؤ‚àڈoچ`‚إ‚«‚éڈَ‘ش‚إ‚ح‚ب‚¢پB
پu‚ب‚ٌ‚ئ‚ـ‚ پv
‚ي‚½‚µ‚ح2•b‚ً‘ز‚½‚¸’ْ‚ك‚½پB‚ـ‚à‚ب‚„M‚³‚ٌ‚ھ‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤپAژش‚©‚çچ~‚è‚é‚ب
‚è
‚è
پu‚ ‚ پB‚±‚è‚ل‚¾‚ك‚¾پv
”ق‚ح1•b‚إ’ْ‚ك‚½پB
پ@”ق‚ح‚و‚–ىچط‚ًژ‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ‚‚ê‚éپB—F’B‚ج“y’n‚ًژط‚è‚ؤچى‚ء‚ؤ‚¢‚é‚»‚¤‚إپA
‘هچھپAگش‚©‚شپA”’چطپAƒTƒjپ[ƒŒƒ^ƒX‚ھ“ü‚ء‚½‘ه‚«‚ب‘ـ‚ً‚ـ‚½‘ص‚پB‚¨‰A‚إ‰ن
‚ھ‰ئ‚ح–ىچط‚ة‚ح•sژ©—R‚µ‚ب‚¢پB‚ ‚è‚ھ‚½‚¢پB
‘هچھپAگش‚©‚شپA”’چطپAƒTƒjپ[ƒŒƒ^ƒX‚ھ“ü‚ء‚½‘ه‚«‚ب‘ـ‚ً‚ـ‚½‘ص‚پB‚¨‰A‚إ‰ن
‚ھ‰ئ‚ح–ىچط‚ة‚ح•sژ©—R‚µ‚ب‚¢پB‚ ‚è‚ھ‚½‚¢پB
پu‚ا‚¤‚µ‚ـ‚·پHپv
پu‚³‚ش‚¢‚ب‚ پB‹A‚ëپv
پu‰a‚ ‚é‚©‚ç•—‚ج“–‚ç‚ب‚¢‚ئ‚±‚ë‚ضچs‚ء‚ؤƒJƒŒƒC‚إ‚à’ق‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚©پv
ڈuژپA–ع‚ج‹ت‚ج“®‚«‚ًژ~‚كپA‚±‚±‚ë‚ً“®‚©‚µ‚½”ق‚إ‚ ‚ء‚½‚ھ
پuƒJƒŒƒC‚à‚³‚ش‚©‚ëپv
ƒJƒŒƒC‚ج‹Cژ‚؟‚ھ‚ي‚©‚ء‚½‚و‚¤‚بٹç‚ً‚µ‚ؤپA‚³‚ء‚³‚ئ‹A‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

پ@‹™ژt‚³‚ٌ‚ة•·‚‚ئ
پu‚±‚ج3,4“ْپA’n•—پi–kگ¼‚ج•—پj‚ھ‹‚¢‚إپB’©‚ج–ش—g‚°‚ھ‚إ‚¯‚ٌ‘D‚à‚ ‚ء‚½‚»
‚¤‚¶‚ل‚يپv
‚¤‚¶‚ل‚يپv
‚ئŒ¾‚¤پB‹™‹¦‚ج‹£‚è‚àڈo‰×‚ھڈ‚ب‚کA“ْچ‚’l‚ً•t‚¯‚ؤ‚¢‚é‚»‚¤‚¾پB‚ي‚½‚µ‚ح
“ھڈم‚ً•‘‚¤“خ(‚ئ‚ٌ‚ر)‚جژp‚ً–ع‚إ’ا‚¢‚ب‚ھ‚ç•—‚ھژ،‚ـ‚ç‚ب‚¢‚à‚ج‚©‚ئ‚µ‚خ‚ç
‚‘ز‚آ‚±‚ئ‚ة‚µ‚½پB3,4“ْ‚à‘±‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ب‚çپA‚»‚ë‚»‚ë“â‚¢‚إ‚à‚¢‚¢‚إ‚ح‚ب‚¢
‚©پB‚»‚ê‚ح1ژٹشŒم‚ج‚±‚ئ‚©‚à’m‚ê‚تپB
“ھڈم‚ً•‘‚¤“خ(‚ئ‚ٌ‚ر)‚جژp‚ً–ع‚إ’ا‚¢‚ب‚ھ‚ç•—‚ھژ،‚ـ‚ç‚ب‚¢‚à‚ج‚©‚ئ‚µ‚خ‚ç
‚‘ز‚آ‚±‚ئ‚ة‚µ‚½پB3,4“ْ‚à‘±‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ب‚çپA‚»‚ë‚»‚ë“â‚¢‚إ‚à‚¢‚¢‚إ‚ح‚ب‚¢
‚©پB‚»‚ê‚ح1ژٹشŒم‚ج‚±‚ئ‚©‚à’m‚ê‚تپB
پ@“خ‚ح‚ي‚½‚µ‚ً‘_‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©پA‚ي‚½‚µ‚ج“ھڈم‚ً‚µ‚«‚è‚ة•‘‚ء‚ؤ‚¢‚éپB•پ’i
Œ©‚邱‚ئ‚ج‚إ‚«‚é—Bˆê‚جƒ^ƒJ‰ب‚ج’¹‚¾پB‹َ’†‚ً—ض‚ً•`‚¢‚ؤ—IپX‚ئ”ٍ‚رپAٹl•¨
‚ًŒ©‚آ‚¯‚é‚₳‚ء‚ئچ~‚è‚ؤ‚³‚ç‚ء‚ؤ‚ن‚پB“خ‚ة–û—g‚°‚ًپA‚جŒ؟‚إ‚¨“éگُ‚ف‚¾پB
Œ©‚邱‚ئ‚ج‚إ‚«‚é—Bˆê‚جƒ^ƒJ‰ب‚ج’¹‚¾پB‹َ’†‚ً—ض‚ً•`‚¢‚ؤ—IپX‚ئ”ٍ‚رپAٹl•¨
‚ًŒ©‚آ‚¯‚é‚₳‚ء‚ئچ~‚è‚ؤ‚³‚ç‚ء‚ؤ‚ن‚پB“خ‚ة–û—g‚°‚ًپA‚جŒ؟‚إ‚¨“éگُ‚ف‚¾پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

پ@‚¢‚آ‚¾‚ء‚½‚©پAژdژ–‚ھ’x‚‚ب‚ء‚ؤ‹ك“¹‚ةگ_ژذ‚ً•à‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚«پA†(‚س‚‚ë
‚¤)‚©‚ç“ھ‚ً‚©‚¶‚ç‚ê‚»‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚éپB‚س‚ي‚è‚ئ†‚ج—¼‘«‚ج’ـ‚ھ“ھ”¯
‚ً‚©‚·‚ء‚½‚ج‚¾پB”w‚ج’ل‚³‚ھچK‚¢‚µ‚½‚ج‚©پA‚©‚¶‚ç‚ê‚ح‚µ‚ب‚©‚ء‚½‚ھپA–ط‚ج
ڈم‚©‚猩‚ؤ‚¢‚é‚ئپAچ•‚‚¸‚ٌ‚®‚肵‚½گ¶‚«•¨‚ھ‚à‚±‚à‚±•à‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپA‚ ‚½
‚©‚àٹiچD‚ج‰a‚ةŒ©‚¦‚½‚ج‚¾‚낤پB‚¢‚ـپA“خ‚ة‚ح‚ا‚¤Œ©‚¦‚é‚ج‚¾‚낤پB‚â‚¢“خپA
پu‚ز‚¢‚ذ‚ه‚ë‚ëپv‚ئ–آ‚¢‚ؤ‚ف‚ëپB
‚¤)‚©‚ç“ھ‚ً‚©‚¶‚ç‚ê‚»‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚éپB‚س‚ي‚è‚ئ†‚ج—¼‘«‚ج’ـ‚ھ“ھ”¯
‚ً‚©‚·‚ء‚½‚ج‚¾پB”w‚ج’ل‚³‚ھچK‚¢‚µ‚½‚ج‚©پA‚©‚¶‚ç‚ê‚ح‚µ‚ب‚©‚ء‚½‚ھپA–ط‚ج
ڈم‚©‚猩‚ؤ‚¢‚é‚ئپAچ•‚‚¸‚ٌ‚®‚肵‚½گ¶‚«•¨‚ھ‚à‚±‚à‚±•à‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپA‚ ‚½
‚©‚àٹiچD‚ج‰a‚ةŒ©‚¦‚½‚ج‚¾‚낤پB‚¢‚ـپA“خ‚ة‚ح‚ا‚¤Œ©‚¦‚é‚ج‚¾‚낤پB‚â‚¢“خپA
پu‚ز‚¢‚ذ‚ه‚ë‚ëپv‚ئ–آ‚¢‚ؤ‚ف‚ëپB
پ@‚ي‚½‚µ‚ح“خ‚جچUŒ‚‚ًŒx‰ْ‚µ‚آ‚آ‚àپA‰“‚”’”g‚ً’‚ك‚ب‚ھ‚ç‚ذ‚ئ‚آ‚ج‚±‚ئ‚ً
چl‚¦ژn‚ك‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚ê‚ح‘D‚إ‰«‚ة‚¢‚é‚ئ‚«پA’أ”g‚ھ‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚½‚ç‚ا‚¤‘خڈˆ‚·
‚ׂ«‚©پA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚¾‚ء‚½پB
چl‚¦ژn‚ك‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚ê‚ح‘D‚إ‰«‚ة‚¢‚é‚ئ‚«پA’أ”g‚ھ‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚½‚ç‚ا‚¤‘خڈˆ‚·
‚ׂ«‚©پA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚¾‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

پ@”gچ‚10‚چپBژ‘¬20‚‹‚چ‚إ‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‰¼’肵‚و‚¤پB‚ي‚½‚µ‚ح—¤‚©‚ç500
‚چ—£‚ꂽگ…گ[30‚چ‚ج‰«چ‡‚¢‚ة‚¢‚éپBپu”ش‚جگ£پv‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚»‚ج•س‚è‚ھ‚¢‚آ‚à‚ج
‚ي‚½‚µ‚جƒ|ƒCƒ“ƒg‚¾پB’أ”g‚ً”F‚ك‚½ژ“_‚إ’أ”g‚ھ‚ي‚½‚µ‚و‚肳‚ç‚ة2‡q‰«‚ة
‚ ‚ء‚½‚ئ‚µ‚و‚¤پB’أ”g‚ح6•ھ‚إ‘D‚ـ‚إ‚â‚ء‚ؤ‚‚é‚©‚çƒAƒ“ƒJپ[‚ًڈم‚°ٹف‚ة“¦‚°
‹A‚éژٹش‚ح‚ب‚¢پBƒAƒ“ƒJپ[‚ًڈم‚°‚é‚ة‚ح10•ھ‚ح•K—v‚¾پBƒAƒ“ƒJپ[‚ًژج‚ؤ‚éژè
‚ح‚ ‚é‚ھپA‚إ‚«‚ê‚خƒAƒ“ƒJپ[‚حژں‚ج’ق‚è‚ج‚½‚ك‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚¨‚«‚½‚¢پB‰ًŒˆچô‚ح
‚ ‚éپB‚ي‚½‚µ‚ح20•ھ‚ـ‚¦‚ة’أ”g‚ً”Œ©‚µ‚ؤ‚¨‚¯‚خ‚و‚¢‚ج‚¾پBƒAƒ“ƒJپ[‚ًڈم
‚°پAٹف‚ة’…‚«ژش‚ً”گi‚³‚¹‚é‚ة‚حڈ[•ھ‚إ‚ ‚éپB‚½‚¾–â‘è‚ب‚ج‚ح20•ھ‚ـ‚¦‚ئ
‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚ê‚خ’أ”g‚ح7‡q‰«چ‡‚¢‚ة‚ ‚邱‚ئ‚ة‚ب‚èپA10‚چ‚جچ‚‚³‚ھŒ©‚¦‚é
‚©‚ا‚¤‚©پB‚ي‚½‚µ‚ح‘oٹل‹¾‚ً•ذژè‚ة’ق‚è‚ً‚â‚ç‚ث‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚إ
‚«‚₵‚ب‚¢پB‚ئ‚·‚é‚ئ“¦‚°‚éژٹش‚ھ‚ب‚¢پB‚»‚ج‚ئ‚«‚ي‚½‚µ‚جژو‚é‚ׂ«چs“®‚ح
‚ب‚ٌ‚¾‚낤پB‚ـ‚¸‚ي‚½‚µ‚حƒ‰ƒCƒtƒWƒƒƒPƒbƒg‚ً2–‡’…‚éپB3–‡‚ح‚©‚³‚خ‚ء‚ؤ’…‚é
‚±‚ئ‚ح‚إ‚«‚ب‚¢‚¾‚낤پB‚à‚؟‚ë‚ٌ‚±‚ê‚ح‹ك‚¢‚¤‚؟‚ةژژ‚µ‚ؤ‚¨‚‚±‚ئ‚ة‚·‚éپB‚»‚ê
‚©‚ç•‚‚«—ض‚ةکr‚ً’ت‚µ•‚‚«—ض‚ھ—£‚ê‚ب‚¢‚و‚¤پAƒچپ[ƒv‚ً‘ج‚ةٹھ‚«‚آ‚¯‚éپBƒN
پ[ƒ‰پ[‚ً‹َ‚ة‚·‚éپB‚±‚ê‚à•‚‚«—ض‘م‚è‚إپA‚ي‚½‚µ‚ح‹›‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚¾‚©‚çپA‹َ
‹C‚ً‹z‚¤‚½‚ك‚ة•‚‚‚±‚ئ‚ھچإ—Dگو‚ب‚ج‚¾پB‚ـ‚½پA“ھ‚ً•غŒى‚·‚邽‚ك‚ةƒwƒ‹ƒپ
ƒbƒg‚ج‘م—p‚ھ•K—v‚¾پB–Xژq‚حٹO‚ê‚ب‚¢‚و‚¤‚ةٹ{‚ذ‚à‚ً•t‚¯‚ؤ‚¨‚پB‚»‚¤‚¾پA3
–‡‚ك‚جƒ‰ƒCƒtƒWƒƒƒPƒbƒg‚ح“ھ‚ة‚©‚ش‚ء‚ؤ‚à‚¢‚¢‚ج‚¾پB4–‡‚ك‚حŒز‚ة’ت‚»‚¤پB‚»
‚ê‚ç•‚‚‚½‚ك‚جٹî–{‘جگ¨‚ً‘f‘پ‚چد‚ـ‚¹‚½‚ئ‚µ‚ؤپA–â‘è‚ح‚±‚ê‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB
‚ي‚½‚µ‚ح‚ا‚±‚ة‚¢‚ê‚خ‚¢‚¢‚ج‚¾‚낤پBƒLƒƒƒrƒ“‚ج’†‚©پA‚ـ‚½‚حژ؛ٹO‚إ‘D‚©‚ç
“ٹ‚°ڈo‚³‚ê‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚µ‚ء‚©‚è‚آ‚©‚ـ‚ء‚ؤ‚¨‚‚ׂ«‚©پBƒLƒƒƒrƒ“‚ح‹@–§گ«‚ھ
چ‚‚پA‘D’ê‚ة‚à‹َ‹Cژ؛‚ھ‚ ‚é‚©‚炵‚خ‚ç‚•‚‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚ح‚¢‚¦پA’¾‚فژn‚ك‚é
‚ئگ…ˆ³‚إڈo‚ç‚ê‚ب‚¢‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚»‚¤‚¾پB‚¢‚âپA’أ”g‚جڈصŒ‚‚ح‘z‘œ‚ً’´‚¦ˆêŒ‚
‚إ‘D‚ح–ط’[”÷گo‚ة‚ب‚é‚©‚à’m‚ê‚ب‚¢پB‘D‚ًژج‚ؤٹف‚ـ‚إ‘S—ح‚إ‚½‚ا‚è’…‚«پA
‚ ‚ئ‚ح‰^‚ً“V‚ة”C‚¹‚é‚ׂ«‚©‚à’m‚ê‚ب‚¢پBƒXƒ}ƒgƒ‰“‡‰«’nگk‚ة‚و‚é’أ”g‚ج
‚¢‚‚آ‚à‚ج‰f‘œ‚ھ”]— ‚ً‰ك‚¬‚éپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
‚چ—£‚ꂽگ…گ[30‚چ‚ج‰«چ‡‚¢‚ة‚¢‚éپBپu”ش‚جگ£پv‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚»‚ج•س‚è‚ھ‚¢‚آ‚à‚ج
‚ي‚½‚µ‚جƒ|ƒCƒ“ƒg‚¾پB’أ”g‚ً”F‚ك‚½ژ“_‚إ’أ”g‚ھ‚ي‚½‚µ‚و‚肳‚ç‚ة2‡q‰«‚ة
‚ ‚ء‚½‚ئ‚µ‚و‚¤پB’أ”g‚ح6•ھ‚إ‘D‚ـ‚إ‚â‚ء‚ؤ‚‚é‚©‚çƒAƒ“ƒJپ[‚ًڈم‚°ٹف‚ة“¦‚°
‹A‚éژٹش‚ح‚ب‚¢پBƒAƒ“ƒJپ[‚ًڈم‚°‚é‚ة‚ح10•ھ‚ح•K—v‚¾پBƒAƒ“ƒJپ[‚ًژج‚ؤ‚éژè
‚ح‚ ‚é‚ھپA‚إ‚«‚ê‚خƒAƒ“ƒJپ[‚حژں‚ج’ق‚è‚ج‚½‚ك‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚¨‚«‚½‚¢پB‰ًŒˆچô‚ح
‚ ‚éپB‚ي‚½‚µ‚ح20•ھ‚ـ‚¦‚ة’أ”g‚ً”Œ©‚µ‚ؤ‚¨‚¯‚خ‚و‚¢‚ج‚¾پBƒAƒ“ƒJپ[‚ًڈم
‚°پAٹف‚ة’…‚«ژش‚ً”گi‚³‚¹‚é‚ة‚حڈ[•ھ‚إ‚ ‚éپB‚½‚¾–â‘è‚ب‚ج‚ح20•ھ‚ـ‚¦‚ئ
‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚ê‚خ’أ”g‚ح7‡q‰«چ‡‚¢‚ة‚ ‚邱‚ئ‚ة‚ب‚èپA10‚چ‚جچ‚‚³‚ھŒ©‚¦‚é
‚©‚ا‚¤‚©پB‚ي‚½‚µ‚ح‘oٹل‹¾‚ً•ذژè‚ة’ق‚è‚ً‚â‚ç‚ث‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚إ
‚«‚₵‚ب‚¢پB‚ئ‚·‚é‚ئ“¦‚°‚éژٹش‚ھ‚ب‚¢پB‚»‚ج‚ئ‚«‚ي‚½‚µ‚جژو‚é‚ׂ«چs“®‚ح
‚ب‚ٌ‚¾‚낤پB‚ـ‚¸‚ي‚½‚µ‚حƒ‰ƒCƒtƒWƒƒƒPƒbƒg‚ً2–‡’…‚éپB3–‡‚ح‚©‚³‚خ‚ء‚ؤ’…‚é
‚±‚ئ‚ح‚إ‚«‚ب‚¢‚¾‚낤پB‚à‚؟‚ë‚ٌ‚±‚ê‚ح‹ك‚¢‚¤‚؟‚ةژژ‚µ‚ؤ‚¨‚‚±‚ئ‚ة‚·‚éپB‚»‚ê
‚©‚ç•‚‚«—ض‚ةکr‚ً’ت‚µ•‚‚«—ض‚ھ—£‚ê‚ب‚¢‚و‚¤پAƒچپ[ƒv‚ً‘ج‚ةٹھ‚«‚آ‚¯‚éپBƒN
پ[ƒ‰پ[‚ً‹َ‚ة‚·‚éپB‚±‚ê‚à•‚‚«—ض‘م‚è‚إپA‚ي‚½‚µ‚ح‹›‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚¾‚©‚çپA‹َ
‹C‚ً‹z‚¤‚½‚ك‚ة•‚‚‚±‚ئ‚ھچإ—Dگو‚ب‚ج‚¾پB‚ـ‚½پA“ھ‚ً•غŒى‚·‚邽‚ك‚ةƒwƒ‹ƒپ
ƒbƒg‚ج‘م—p‚ھ•K—v‚¾پB–Xژq‚حٹO‚ê‚ب‚¢‚و‚¤‚ةٹ{‚ذ‚à‚ً•t‚¯‚ؤ‚¨‚پB‚»‚¤‚¾پA3
–‡‚ك‚جƒ‰ƒCƒtƒWƒƒƒPƒbƒg‚ح“ھ‚ة‚©‚ش‚ء‚ؤ‚à‚¢‚¢‚ج‚¾پB4–‡‚ك‚حŒز‚ة’ت‚»‚¤پB‚»
‚ê‚ç•‚‚‚½‚ك‚جٹî–{‘جگ¨‚ً‘f‘پ‚چد‚ـ‚¹‚½‚ئ‚µ‚ؤپA–â‘è‚ح‚±‚ê‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB
‚ي‚½‚µ‚ح‚ا‚±‚ة‚¢‚ê‚خ‚¢‚¢‚ج‚¾‚낤پBƒLƒƒƒrƒ“‚ج’†‚©پA‚ـ‚½‚حژ؛ٹO‚إ‘D‚©‚ç
“ٹ‚°ڈo‚³‚ê‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚µ‚ء‚©‚è‚آ‚©‚ـ‚ء‚ؤ‚¨‚‚ׂ«‚©پBƒLƒƒƒrƒ“‚ح‹@–§گ«‚ھ
چ‚‚پA‘D’ê‚ة‚à‹َ‹Cژ؛‚ھ‚ ‚é‚©‚炵‚خ‚ç‚•‚‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚ح‚¢‚¦پA’¾‚فژn‚ك‚é
‚ئگ…ˆ³‚إڈo‚ç‚ê‚ب‚¢‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚»‚¤‚¾پB‚¢‚âپA’أ”g‚جڈصŒ‚‚ح‘z‘œ‚ً’´‚¦ˆêŒ‚
‚إ‘D‚ح–ط’[”÷گo‚ة‚ب‚é‚©‚à’m‚ê‚ب‚¢پB‘D‚ًژج‚ؤٹف‚ـ‚إ‘S—ح‚إ‚½‚ا‚è’…‚«پA
‚ ‚ئ‚ح‰^‚ً“V‚ة”C‚¹‚é‚ׂ«‚©‚à’m‚ê‚ب‚¢پBƒXƒ}ƒgƒ‰“‡‰«’nگk‚ة‚و‚é’أ”g‚ج
‚¢‚‚آ‚à‚ج‰f‘œ‚ھ”]— ‚ً‰ك‚¬‚éپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

ٹ£‚¢‚½‹َ‚ة‰_‚ح‚؟‚ہ‚êپAگط‚ê–ع‚©‚ç‚·‚«‚ـ•—‚ج‚و‚¤‚ة•—‚ً‘—‚èچ‚ٌ‚إ‚
‚éپB‰«‚ج”’”g‚ح’ء‚ـ‚è‚»‚¤‚à‚ب‚¢پB‹™‘D‚ھ“¦‚°چ‚ق‚و‚¤‚ةچ`‚ة“ü‚ء‚ؤ—ˆ‚½پB
“خ‚ح‚ي‚½‚µ‚جژvچl‚ة•t‚«چ‡‚¢‚«‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚©پA‚¢‚آ‚ج‚ـ‚ة‚©ژp‚ًڈء‚µپA
’ç–h‚ج’ق‚èگl‚حˆّ‚«’ھ‚ة“ü‚ء‚½‚±‚ئ‚ً’m‚èپA“¹‹ï‚ً‚½‚½‚فژn‚ك‚ؤ‚¢‚éپB
‚éپB‰«‚ج”’”g‚ح’ء‚ـ‚è‚»‚¤‚à‚ب‚¢پB‹™‘D‚ھ“¦‚°چ‚ق‚و‚¤‚ةچ`‚ة“ü‚ء‚ؤ—ˆ‚½پB
“خ‚ح‚ي‚½‚µ‚جژvچl‚ة•t‚«چ‡‚¢‚«‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚©پA‚¢‚آ‚ج‚ـ‚ة‚©ژp‚ًڈء‚µپA
’ç–h‚ج’ق‚èگl‚حˆّ‚«’ھ‚ة“ü‚ء‚½‚±‚ئ‚ً’m‚èپA“¹‹ï‚ً‚½‚½‚فژn‚ك‚ؤ‚¢‚éپB
پ@‚l‚³‚ٌ‚ح‚à‚¤àxà(‚±‚½‚آ)‚إ”M‚¢‚¨’ƒ‚إ‚àˆù‚ٌ‚إ‚¢‚邾‚낤پB
پ@ƒJƒŒƒC‚ح‚ظ‚ٌ‚ئ‚¤‚ةٹ¦‚ھ‚è‚ب‚ٌ‚¾‚낤‚©پB“خ‚جچs•û‚ً‹C‚ة‚µ‚ب‚ھ‚ç‚ي‚½‚µ‚ح
‚ـ‚¾‚±‚ê‚©‚ç‚جگg‚جگU‚è•û‚ً’è‚ك‚«‚ê‚ب‚¢‚إ‚¢‚½پB
‚ـ‚¾‚±‚ê‚©‚ç‚جگg‚جگU‚è•û‚ً’è‚ك‚«‚ê‚ب‚¢‚إ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@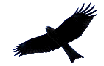
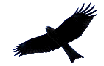
پ@‹†‹ة‚جژhگg
پ@‹›‚ھ’ق‚ê‚é‚ئ•X‚ج“ü‚ء‚½ƒNپ[ƒ‰پ[‚ة•ْ‚èچ‚ف‘N“x‚ً•غ‚؟ژ‚؟‹A‚éپB‚±‚ê‚ح
•پ’ت‚ج‚â‚è•ûپB‚±‚ê‚ًˆê•à‘Oگi‚³‚¹‚ؤ’ق‚ê‚é‚ئ‚·‚®‚ة’÷‚ك‚ؤƒNپ[ƒ‰پ[‚ضپB’÷
‚ك‚éپA‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حŒz“®–¬‚ً•ï’ڑ‚إ‚©‚«گط‚èˆêڈu‚ج‚¤‚؟‚ةژE‚·‚±‚ئ‚ًŒ¾‚¤پBŒz
“®–¬‚ة•ï’ڑ‚ً“ü‚ê‚é‚ئپAگK”ِ‚حŒy‚لz¹‚µ‚ا‚ë‚è‚ئ”S“y‚ج‚و‚¤‚بچ•‚¸‚ٌ‚¾ŒŒ
‚ج‰ٍ‚ھڈo‚éپB‘ج“à‚ةŒŒ‰t‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚©‚ç’÷‚ك‚ب‚¢ڈêچ‡‚ئ”ن‚×پAڈL‚ف‚ج
‚ب‚¢–،‚ئگg‚ج’÷‚ـ‚è‚ھٹi’i‚ة‚؟‚ھ‚¤پB
•پ’ت‚ج‚â‚è•ûپB‚±‚ê‚ًˆê•à‘Oگi‚³‚¹‚ؤ’ق‚ê‚é‚ئ‚·‚®‚ة’÷‚ك‚ؤƒNپ[ƒ‰پ[‚ضپB’÷
‚ك‚éپA‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حŒz“®–¬‚ً•ï’ڑ‚إ‚©‚«گط‚èˆêڈu‚ج‚¤‚؟‚ةژE‚·‚±‚ئ‚ًŒ¾‚¤پBŒz
“®–¬‚ة•ï’ڑ‚ً“ü‚ê‚é‚ئپAگK”ِ‚حŒy‚لz¹‚µ‚ا‚ë‚è‚ئ”S“y‚ج‚و‚¤‚بچ•‚¸‚ٌ‚¾ŒŒ
‚ج‰ٍ‚ھڈo‚éپB‘ج“à‚ةŒŒ‰t‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚©‚ç’÷‚ك‚ب‚¢ڈêچ‡‚ئ”ن‚×پAڈL‚ف‚ج
‚ب‚¢–،‚ئگg‚ج’÷‚ـ‚è‚ھٹi’i‚ة‚؟‚ھ‚¤پB
پ@‚±‚ê‚ً‚³‚ç‚ةگi‰»‚³‚¹‚½‚ج‚ھٹˆ‚«‚½‚ـ‚ـ‚جژ‚؟‹A‚è‚إ‚ ‚éپBٹCگ…‚ً—eٹي‚ة
“ü‚êپAژ_Œ‡‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢‚و‚¤‚ةƒGƒAپ[ƒ|ƒ“ƒv‚إژ_‘f‚ً‘—‚èچ‚قپB‚±‚±‚ـ‚إ‚ح’N
‚ة‚إ‚àژv‚¢‚آ‚«‚»‚¤‚¾پB‚µ‚©‚µˆع“®ژ‚ة—eٹي‚©‚çٹCگ…‚ھکR‚ê‚ؤ‚ح‘ه•د‚¾پB
‹A‚è’…‚¢‚½‚ئ‚«ƒgƒ‰ƒ“ƒN‚ھگ…گZ‚µ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚حچ¢‚éپB‚ـ‚½ƒgƒ‰ƒ“ƒN“à
‚ح‰ؤڈêپA‚©‚ب‚è‹C‰·‚ھڈمڈ¸‚·‚éپBژ_‘f‚حڈ\•ھ‚إ‚àٹCگ…‚ھ‚¨“’‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ
‚¤‚µپA“~‹G‚ح‹t‚ة’ل‰؛‚·‚é‹°‚ê‚ھ‚ ‚éپB‚±‚ê‚إ‚ح‹›‚حگ¶‚«‰„‚ر‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«
‚ب‚¢پB‘–چs’†‚ج—h‚ê‚ةکR‚ê‚ب‚¢‚±‚ئپAٹO‹C‚ة‰e‹؟‚³‚ê‚ب‚¢‚±‚ئپA‚ھ•K—vڈً
Œڈ‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚ة‚ ‚é’ِ“x‘ه‚«‚‚ب‚‚ؤ‚حپB
“ü‚êپAژ_Œ‡‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢‚و‚¤‚ةƒGƒAپ[ƒ|ƒ“ƒv‚إژ_‘f‚ً‘—‚èچ‚قپB‚±‚±‚ـ‚إ‚ح’N
‚ة‚إ‚àژv‚¢‚آ‚«‚»‚¤‚¾پB‚µ‚©‚µˆع“®ژ‚ة—eٹي‚©‚çٹCگ…‚ھکR‚ê‚ؤ‚ح‘ه•د‚¾پB
‹A‚è’…‚¢‚½‚ئ‚«ƒgƒ‰ƒ“ƒN‚ھگ…گZ‚µ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚حچ¢‚éپB‚ـ‚½ƒgƒ‰ƒ“ƒN“à
‚ح‰ؤڈêپA‚©‚ب‚è‹C‰·‚ھڈمڈ¸‚·‚éپBژ_‘f‚حڈ\•ھ‚إ‚àٹCگ…‚ھ‚¨“’‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ
‚¤‚µپA“~‹G‚ح‹t‚ة’ل‰؛‚·‚é‹°‚ê‚ھ‚ ‚éپB‚±‚ê‚إ‚ح‹›‚حگ¶‚«‰„‚ر‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«
‚ب‚¢پB‘–چs’†‚ج—h‚ê‚ةکR‚ê‚ب‚¢‚±‚ئپAٹO‹C‚ة‰e‹؟‚³‚ê‚ب‚¢‚±‚ئپA‚ھ•K—vڈً
Œڈ‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚ة‚ ‚é’ِ“x‘ه‚«‚‚ب‚‚ؤ‚حپB
پu‚¢‚¢—eٹي‚ح‚ب‚¢‚à‚ج‚©پv
ƒoƒPƒc‚âƒvƒ‰ƒXƒeƒBƒbƒN‚ج—eٹي‚حٹO‹C‰·‚ة•qٹ´‚إگ…‰·‚ة•د‰»‚ًگ¶‚¶‚éپBƒKƒ‰
ƒX‚جگ…‘…‚حٹW‚ھ‚ب‚گ…کR‚ê‚ھگS”z‚¾پB
ƒX‚جگ…‘…‚حٹW‚ھ‚ب‚گ…کR‚ê‚ھگS”z‚¾پB
پ@‚»‚ê‚حگg‹ك‚ة‚ ‚ء‚½پB‚¢‚آ‚àژg‚ء‚ؤ‚¢‚éƒNپ[ƒ‰پ[‚إ‚ ‚éپBٹO‹C‚ئژص’f‚³‚êپA
‚µ‚©‚àٹW‚ج“à‘¤‚ة‚حƒSƒ€¥ƒpƒbƒLƒ“‚ھ•t‚¢‚ؤ‚¢‚ؤپAٹ®‘S‚ة–§’…‚³‚ê‚éپB–â‘è
‚حƒGƒAپ[ƒ|ƒ“ƒv‚ج‘}“ü‚¾پB“d’rژ®‚ج–{‘ج‚©‚çƒ`ƒ…پ[ƒu‚إژ_‘f‚ً‘—‚é‚ي‚¯‚¾
‚ھپA–{‘ج‚ً”G‚ç‚·‚ئŒجڈل‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB
‚µ‚©‚àٹW‚ج“à‘¤‚ة‚حƒSƒ€¥ƒpƒbƒLƒ“‚ھ•t‚¢‚ؤ‚¢‚ؤپAٹ®‘S‚ة–§’…‚³‚ê‚éپB–â‘è
‚حƒGƒAپ[ƒ|ƒ“ƒv‚ج‘}“ü‚¾پB“d’rژ®‚ج–{‘ج‚©‚çƒ`ƒ…پ[ƒu‚إژ_‘f‚ً‘—‚é‚ي‚¯‚¾
‚ھپA–{‘ج‚ً”G‚ç‚·‚ئŒجڈل‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB
پ@‚ي‚½‚µ‚حƒNپ[ƒ‰پ[‚جٹO‘¤ڈم•”‚ةƒ`ƒ…پ[ƒu‚ً’ت‚·‚½‚ك‚جŒٹ‚ًƒhƒٹƒ‹‚إٹJ‚¯
‚½پBƒvƒ‰ƒXƒeƒBƒbƒN‚ج“ٌڈdچ\‘¢‚إ’†‚ة”–AƒXƒ`ƒچپ[ƒ‹‚ھ‹l‚ك‚ؤ‚ ‚éپBŒٹ‚ح‹ء
‚‚ظ‚اٹب’P‚ةٹJ‚¢‚½پBƒNپ[ƒ‰پ[ٹO‘¤ڈم•”‚ة–{‘ج‚ًƒrƒjپ[ƒ‹ƒeپ[ƒv‚إŒإ’肵پA
Œٹ‚©‚çƒ`ƒ…پ[ƒu‚ً’ت‚·پB‚±‚ê‚àٹب’P‚¾پBŒٹ‚ئƒ`ƒ…پ[ƒu‚جŒ„ٹش‚ً‚â‚ح‚èƒrƒjپ[
ƒ‹ƒeپ[ƒv‚إ–„‚ك‚½پB
‚½پBƒvƒ‰ƒXƒeƒBƒbƒN‚ج“ٌڈdچ\‘¢‚إ’†‚ة”–AƒXƒ`ƒچپ[ƒ‹‚ھ‹l‚ك‚ؤ‚ ‚éپBŒٹ‚ح‹ء
‚‚ظ‚اٹب’P‚ةٹJ‚¢‚½پBƒNپ[ƒ‰پ[ٹO‘¤ڈم•”‚ة–{‘ج‚ًƒrƒjپ[ƒ‹ƒeپ[ƒv‚إŒإ’肵پA
Œٹ‚©‚çƒ`ƒ…پ[ƒu‚ً’ت‚·پB‚±‚ê‚àٹب’P‚¾پBŒٹ‚ئƒ`ƒ…پ[ƒu‚جŒ„ٹش‚ً‚â‚ح‚èƒrƒjپ[
ƒ‹ƒeپ[ƒv‚إ–„‚ك‚½پB
پ@‚¢‚و‚¢‚وژہ‘H“–“ْپB‚ي‚½‚µ‚ح’ق‚ء‚½‹›‚ً‘D‚جگ¶âإ‚إٹˆ‚©‚µ‚ؤ‚¨‚«پAچ`‚ة–ك
‚ء‚ؤƒNپ[ƒ‰پ[‚ةƒoƒPƒc“ٌ”t‚ئ”¼•ھ‚جٹCگ…‚ً“ü‚ꂽپB–{‘ج‚ةƒXƒCƒbƒ`‚ً“ü‚ê‚é
‚ئ—\چs‰‰ڈK‚ا‚¨‚èپAƒuƒNƒuƒN‚ئ‹َ‹C‚ج–A‚ھٹCگ…‚ةچs‚«‚ي‚½‚éپB‚»‚µ‚ؤٹˆ‚«‚ج
‚¢‚¢ƒAƒW‚ًگ¶âإ‚©‚ç5•Cˆع‚µٹW‚ً•آ‚ك‚½پBژ_‘f‚ً‘—‚葱‚¯‚éگS’n‚و‚¢ƒ|ƒ“ƒv
‚جڈ¬چڈ‚ف‚إ’ل‚¢‰¹‚ھ’Bگ¬ٹ´‚ً–‚½‚µ‚½پB
‚ء‚ؤƒNپ[ƒ‰پ[‚ةƒoƒPƒc“ٌ”t‚ئ”¼•ھ‚جٹCگ…‚ً“ü‚ꂽپB–{‘ج‚ةƒXƒCƒbƒ`‚ً“ü‚ê‚é
‚ئ—\چs‰‰ڈK‚ا‚¨‚èپAƒuƒNƒuƒN‚ئ‹َ‹C‚ج–A‚ھٹCگ…‚ةچs‚«‚ي‚½‚éپB‚»‚µ‚ؤٹˆ‚«‚ج
‚¢‚¢ƒAƒW‚ًگ¶âإ‚©‚ç5•Cˆع‚µٹW‚ً•آ‚ك‚½پBژ_‘f‚ً‘—‚葱‚¯‚éگS’n‚و‚¢ƒ|ƒ“ƒv
‚جڈ¬چڈ‚ف‚إ’ل‚¢‰¹‚ھ’Bگ¬ٹ´‚ً–‚½‚µ‚½پB
پ@‹A‚è’…‚‚ـ‚إگ…کR‚ê‚ھ‹C‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پBڈم‚èچâ‚ ‚è‹}’âژ~‚ ‚èƒJپ[ƒu‚ ‚è
‚¾‚©‚çڈ‚µ‚حکR‚ê‚ؤ‚¢‚邾‚낤پBڈ‚µ‚©‘ه—ت‚ة‚©‚¾پB‚»‚ê‚ھ–â‘肾‚ء‚½پB‚ئ‚±
‚ë‚ھ‚ب‚ٌ‚ئگ…کR‚ê‚حٹF–³‚إƒ|ƒ“ƒv‚àڈ\•ھ‹@”\‚µپA‹›‚حƒsƒ“ƒsƒ“‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
‚¾‚©‚çڈ‚µ‚حکR‚ê‚ؤ‚¢‚邾‚낤پBڈ‚µ‚©‘ه—ت‚ة‚©‚¾پB‚»‚ê‚ھ–â‘肾‚ء‚½پB‚ئ‚±
‚ë‚ھ‚ب‚ٌ‚ئگ…کR‚ê‚حٹF–³‚إƒ|ƒ“ƒv‚àڈ\•ھ‹@”\‚µپA‹›‚حƒsƒ“ƒsƒ“‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚»‚جژhگg‚ج‚¤‚ـ‚©‚ء‚½‚±‚ئپB’÷‚ك‚ؤژ‚ء‚ؤ‹A‚ء‚½‹›‚ح‚¤‚ـ‚¢پA‚ئگمŒغ‘إ‚ء‚ؤ
‚¢‚½‚ج‚¾‚ھپA‚»‚ج”ن‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚ب‚ٌ‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚àگg‚ج’÷‚ـ‚è‚ھگ”’i‚؟‚ھ‚¤پBƒR
ƒVƒRƒV‚µ‚ؤ‚¢‚ؤٹڑ‚ـ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ب‚¢پB‚±‚ê‚ـ‚إ‚جژhگg‚حژ•‚ھگg‚ً‰ں‚µ’ׂ·ٹ´
‚¶‚¾‚ء‚½‚ھپA‚±‚ê‚حگط‚è—ô‚‚و‚¤‚ةٹ´‚¶‚ç‚ꂽپBگ¶âإ—؟—“X‚إ‚ج‹›‚à‚±‚¤‚ب‚ج
‚©پB‚»‚¤‚إ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ھ‘½‚¢پB‚ب‚؛‚ب‚ç—؟—“X‚ج‹›‚حگ”“ْٹشگ¶âإ‚إگ¶‚«‚ؤ‚¢‚é
‚¤‚؟پA‹ط“÷‚ھگٹ‚¦‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
‚¢‚½‚ج‚¾‚ھپA‚»‚ج”ن‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚ب‚ٌ‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚àگg‚ج’÷‚ـ‚è‚ھگ”’i‚؟‚ھ‚¤پBƒR
ƒVƒRƒV‚µ‚ؤ‚¢‚ؤٹڑ‚ـ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ب‚¢پB‚±‚ê‚ـ‚إ‚جژhگg‚حژ•‚ھگg‚ً‰ں‚µ’ׂ·ٹ´
‚¶‚¾‚ء‚½‚ھپA‚±‚ê‚حگط‚è—ô‚‚و‚¤‚ةٹ´‚¶‚ç‚ꂽپBگ¶âإ—؟—“X‚إ‚ج‹›‚à‚±‚¤‚ب‚ج
‚©پB‚»‚¤‚إ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ھ‘½‚¢پB‚ب‚؛‚ب‚ç—؟—“X‚ج‹›‚حگ”“ْٹشگ¶âإ‚إگ¶‚«‚ؤ‚¢‚é
‚¤‚؟پA‹ط“÷‚ھگٹ‚¦‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@ƒGƒAپ[ƒ|ƒ“ƒv‚إژY’n’¼‘—پB‚»‚ê‚ھ‹†‹ة‚جژhگg‚©پB‚»‚¤‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚³‚ç‚ة‹†
‹ة‚جژhگg‚ً’ا‹پ‚µ‚و‚¤پB’ق‚èگl‚µ‚©–،‚ي‚¦‚ب‚¢‹†‹ة‚جژhگg‚ًپB
‹ة‚جژhگg‚ً’ا‹پ‚µ‚و‚¤پB’ق‚èگl‚µ‚©–،‚ي‚¦‚ب‚¢‹†‹ة‚جژhگg‚ًپB
پ@‚»‚ê‚ح’ق‚èڈم‚°‚½‚ç‚»‚جڈêپAٹش”¯“ü‚ꂸژhگg‚ة‚µپAگH‚·‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB‹™ژt
‚ھ‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ة‚³‚ç‚ة‚ذ‚ئچH•vچl‚¦‚ؤ‚ ‚éپB’ق‚èڈم‚°‚½‚çگ¶âإ‚ة‚à“ü‚ꂸ
‘Dڈ°‚ة‚à’…’n‚³‚¹‚¸پAگj‚©‚ç•ï’ڑ‚ضƒٹƒŒپ[‚·‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
‚ھ‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ة‚³‚ç‚ة‚ذ‚ئچH•vچl‚¦‚ؤ‚ ‚éپB’ق‚èڈم‚°‚½‚çگ¶âإ‚ة‚à“ü‚ꂸ
‘Dڈ°‚ة‚à’…’n‚³‚¹‚¸پAگj‚©‚ç•ï’ڑ‚ضƒٹƒŒپ[‚·‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
پu‚»‚¤‚¢‚¤‚±‚ئ‚¾‚©‚çژں‰ٌ‚حژhگg•ï’ڑ—pˆس‚µ‚ؤ—ˆ‚ؤ‚‚êپv
ژhگg‚ًڈمژè‚ةچى‚ê‚ب‚¢‚ي‚½‚µ‚ح—Fگl‚ة“dکb‚ً“ü‚ꂽپB
پu‚»‚è‚ل‚ پA‚·‚²‚¢‚إ‚·‚ثپB‚â‚è‚ـ‚µ‚ه‚¤پB“ءڈم‚جƒrپ[ƒ‹‚àژ‚ء‚ؤچs‚«‚ـ‚µ‚ه‚¤پv
پu‚¤‚ٌپA‚¤‚ٌپBƒrپ[ƒ‹‚ح‚ي‚½‚µ‚ھژ‚ء‚ؤچs‚«‚ـ‚µ‚ه‚¤پv
‚ي‚½‚µ‚ح•rƒrپ[ƒ‹‚ًژ‚ء‚ؤچs‚‚آ‚à‚肾پB‚»‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àژ†ƒRƒbƒv‚¶‚لپA‹»‚´‚ك
‚¾‚بپB
‚¾‚بپB
پ@—Fگl‚ج•ï’ڑ‚ح‚و‚ظ‚اگط‚ê–،‚ھ‚و‚¢‚ج‚©پA•ï’ڑ‚جگو‚ًگV•·‚جچLچگژ†‚إٹھ
‚«ƒZƒچƒeپ[ƒv‚ًٹôڈd‚ة‚à“\‚èپA’e‚جچ‚ك‚ç‚ꂽ“S–C‚إ‚àژ‚؟‰^‚ش‚و‚¤‚ةگTڈd
‚ةƒoƒbƒO‚ج’ê‚ة”[‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پB‚ي‚½‚µ‚حƒOƒ‰ƒX‚ً—â“€Œة‚إ—â‚₵پAƒrپ[ƒ‹
‚ئ‚ئ‚à‚ةƒNپ[ƒ‰پ[‚ج•X‚إ—â‚₵‚ؤ‚¢‚éپB
‚«ƒZƒچƒeپ[ƒv‚ًٹôڈd‚ة‚à“\‚èپA’e‚جچ‚ك‚ç‚ꂽ“S–C‚إ‚àژ‚؟‰^‚ش‚و‚¤‚ةگTڈd
‚ةƒoƒbƒO‚ج’ê‚ة”[‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پB‚ي‚½‚µ‚حƒOƒ‰ƒX‚ً—â“€Œة‚إ—â‚₵پAƒrپ[ƒ‹
‚ئ‚ئ‚à‚ةƒNپ[ƒ‰پ[‚ج•X‚إ—â‚₵‚ؤ‚¢‚éپB
پ@‘وˆê“ٹ‚ح—z‚ھڈ‚µŒX‚«‚©‚¯‚½چ پB
پuڈt‚ف‚½‚¢‚â‚ثپv
ژR‚جچg—t‚ھژU‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚±‚جچ ‚ة‚µ‚ؤ‚حپA•—‚à”g‚à‚ب‚’g‚©‚¢—z‹C‚¾پB
پuچإچ‚‚ج“ْکa‚â‚ثپv
چإچ‚پA‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح‚â‚ھ‚ؤ’ق‚ê‚é‚إ‚ ‚낤‘هƒAƒWپA‚»‚µ‚ؤپA‹†‹ة‚جژhگg‚ض‚جژ^
ژ«‚ً‚àٹـ‚ٌ‚إ‚¢‚½پB
ژ«‚ً‚àٹـ‚ٌ‚إ‚¢‚½پB
پ@‚ئ‚±‚ë‚ھ’ق‚ê‚ب‚¢پBƒtƒO‚à‹à‹›‚àƒپƒ_ƒJ‚à’ق‚ê‚ب‚¢پB‚µ‚خ‚ç‚Œo‚ء‚ؤ—Fگl‚ح
پu‚±‚±‚ح‚ـ‚¦‚ئ‚؟‚ه‚ء‚ئڈêڈٹ‚ھ‚؟‚ھ‚¤پv
‚ئŒ¾‚¢ڈo‚µ‚½پB
پu‚¢‚¢‚⓯‚¶ƒ|ƒCƒ“ƒg‚وپBگ…گ[‚à‚ز‚ء‚½‚è18ƒپپ[ƒgƒ‹‚¾‚ء‚½پB”چ‚°‚ؤگش“y‚ھکI
ڈo‚µ‚½ٹR‚ف‚¢‚½‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éٹف‚ھگ³–ت‚¾‚µپAŒü‚¤‚ةگش‚¢‰®چھ‚ج‰ئ‚ھŒ©‚¦‚é
‚¾‚낤پB‚ ‚ء‚؟‚ة‚ح—خ‚ج‰®چھپB‚±‚جگü‚ًŒ‹‚ٌ‚¾‚±‚±پA‚»‚µ‚ؤگ…گ[پB‚ز‚ء‚½‚肱
‚±‚âپv
ڈo‚µ‚½ٹR‚ف‚¢‚½‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éٹف‚ھگ³–ت‚¾‚µپAŒü‚¤‚ةگش‚¢‰®چھ‚ج‰ئ‚ھŒ©‚¦‚é
‚¾‚낤پB‚ ‚ء‚؟‚ة‚ح—خ‚ج‰®چھپB‚±‚جگü‚ًŒ‹‚ٌ‚¾‚±‚±پA‚»‚µ‚ؤگ…گ[پB‚ز‚ء‚½‚肱
‚±‚âپv
‚»‚¤گà–¾‚µ‚ؤ‚à”[“¾‚ھ‚¢‚©‚ب‚¢‚و‚¤‚·‚¾پB‚ي‚½‚µ‚ح‹C‚ھگi‚ـ‚ب‚©‚ء‚½‚ھ‹C•ھ
“]ٹ·‚ج‚½‚ك‚ة‘¼‚جƒ|ƒCƒ“ƒg‚ض‘D‚ً“®‚©‚µ‚½پB
“]ٹ·‚ج‚½‚ك‚ة‘¼‚جƒ|ƒCƒ“ƒg‚ض‘D‚ً“®‚©‚µ‚½پB
پ@‚ي‚½‚µ‚ج’ق‚èگMڈً‚ح’ق‚ê‚ب‚‚ؤ‚àگh•ّ‹‚‰a‚ً“ٹ“ü‘±‚¯‚邱‚ئپBƒAƒW‚ح‰ٌ
—V‹›‚¾‚©‚ç‚ ‚é’ِ“xƒ|ƒCƒ“ƒg‚ھ‚¸‚ê‚ؤ‚¢‚ؤ‚àٹٌ‚ء‚ؤ‚‚é‚à‚ج‚¾‚ئگM‚¶‚ؤ‚¢‚éپB
ƒAƒW‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢پBƒ`ƒk‚â‘â‚ج’ꕨ‚à‰a‚ھٹC’ê‚ة—‚ـ‚è•Y‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئپA‰“‚
‚©‚çˆّ‚«ٹٌ‚¹‚ç‚ê’ق‚êژn‚ك‚é‚ج‚¾پB‰ت‚µ‚ؤ—[•û‚ـ‚إ‚س‚½‚è‹C‚ً“f‚¢‚ؤپAƒAƒW
‚حژhگg‚ة‚ح‚إ‚«‚ب‚¢‚ظ‚اڈ¬‚³‚ب‚à‚ج‚خ‚©‚è‚إ‚·‚ׂؤ•ْ‚µ‚ؤ‚ ‚°‚½پB
—V‹›‚¾‚©‚ç‚ ‚é’ِ“xƒ|ƒCƒ“ƒg‚ھ‚¸‚ê‚ؤ‚¢‚ؤ‚àٹٌ‚ء‚ؤ‚‚é‚à‚ج‚¾‚ئگM‚¶‚ؤ‚¢‚éپB
ƒAƒW‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢پBƒ`ƒk‚â‘â‚ج’ꕨ‚à‰a‚ھٹC’ê‚ة—‚ـ‚è•Y‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئپA‰“‚
‚©‚çˆّ‚«ٹٌ‚¹‚ç‚ê’ق‚êژn‚ك‚é‚ج‚¾پB‰ت‚µ‚ؤ—[•û‚ـ‚إ‚س‚½‚è‹C‚ً“f‚¢‚ؤپAƒAƒW
‚حژhگg‚ة‚ح‚إ‚«‚ب‚¢‚ظ‚اڈ¬‚³‚ب‚à‚ج‚خ‚©‚è‚إ‚·‚ׂؤ•ْ‚µ‚ؤ‚ ‚°‚½پB
پ@—z‚ھ’كŒ©ٹx‚ة‰B‚ê’ç–h‚ةˆع‚ء‚½پB“ث’[‚ةگش‚¢“d‹…‚جŒُ‚é‚kژڑ‚جڈ‚µٹJ‚¢
‚½Œ`‚ج’ç–h‚¾پBٹف‚©‚ç—£‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپu—£‚ê’ç–hپv‚ئŒ¾‚¢پA‰؛ٹE‚ئ‚ح–³‰ڈ‚ج
ژ©—R‚ب‹C•ھ‚ة‚ب‚ê‚éپB—c‚¢‚±‚ëپA‚ف‚©‚ٌ” ‚ة“ü‚ء‚ؤ‚ذ‚ئ‚è‚جگ¢ٹE‚ةگZ‚ء‚½‚»
‚ٌ‚ب‹C•ھ‚ًژv‚¢ڈo‚·پB
‚½Œ`‚ج’ç–h‚¾پBٹف‚©‚ç—£‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپu—£‚ê’ç–hپv‚ئŒ¾‚¢پA‰؛ٹE‚ئ‚ح–³‰ڈ‚ج
ژ©—R‚ب‹C•ھ‚ة‚ب‚ê‚éپB—c‚¢‚±‚ëپA‚ف‚©‚ٌ” ‚ة“ü‚ء‚ؤ‚ذ‚ئ‚è‚جگ¢ٹE‚ةگZ‚ء‚½‚»
‚ٌ‚ب‹C•ھ‚ًژv‚¢ڈo‚·پB
پ@–é’ق‚èٹJژnپB‚¢‚âپA‚»‚ج‚ـ‚¦‚ة’ق‚ء‚½‹›‚إ“ç‚ً‚·‚é‚ح‚¸‚¾‚ء‚½پBƒJƒڈƒnƒM
‚âƒAƒ‰ƒJƒu‚ً“ü‚ê‚é‚ج‚إپA‚¨‚¢‚µ‚¢ƒXپ[ƒv‚ھ‚إ‚«‚é—\’肾‚ء‚½پB—Fگl‚حژhگg
‚àڈمژ肾‚ھ“ç—؟—‚â–،‘Xڈ`پAƒoپ[ƒxƒLƒ…پ[‚ب‚ا‚àƒLƒƒƒ“ƒv‚ج‚ئ‚«‚ح–ظپX‚ئ
چى‚ء‚ؤ‚‚ê‚éپBƒAƒEƒgƒhƒA”h‚إƒKƒXƒRƒ“ƒچپAƒtƒ‰ƒCƒpƒ“پA“ç‚ب‚اƒRƒ“ƒpƒNƒg‚ب“¹
‹ï‚ً‚½‚‚³‚ٌ‘µ‚¦‚ؤ‚¢‚éپB‚ي‚½‚µ‚ح–ىچط‚ًگô‚ء‚½‚èژè“`‚¤‚±‚ئ‚à‚ ‚é‚ھپAƒ|ƒP
ƒbƒg‚ةژè‚ً“ث‚ءچ‚ٌ‚إŒ©‚ؤ‚¢‚邾‚¯‚ج‚ظ‚¤‚ھ‘½‚¢پBچ،–é‚ج“ç‚ح–ىچط‚©‚çںّ
‚فڈo‚½‚³‚ç‚è‚ئ‚µ‚½ژ‰‹C‚ج‚ب‚¢ƒXپ[ƒv‚ئ‚ب‚ء‚½پB
‚âƒAƒ‰ƒJƒu‚ً“ü‚ê‚é‚ج‚إپA‚¨‚¢‚µ‚¢ƒXپ[ƒv‚ھ‚إ‚«‚é—\’肾‚ء‚½پB—Fگl‚حژhگg
‚àڈمژ肾‚ھ“ç—؟—‚â–،‘Xڈ`پAƒoپ[ƒxƒLƒ…پ[‚ب‚ا‚àƒLƒƒƒ“ƒv‚ج‚ئ‚«‚ح–ظپX‚ئ
چى‚ء‚ؤ‚‚ê‚éپBƒAƒEƒgƒhƒA”h‚إƒKƒXƒRƒ“ƒچپAƒtƒ‰ƒCƒpƒ“پA“ç‚ب‚اƒRƒ“ƒpƒNƒg‚ب“¹
‹ï‚ً‚½‚‚³‚ٌ‘µ‚¦‚ؤ‚¢‚éپB‚ي‚½‚µ‚ح–ىچط‚ًگô‚ء‚½‚èژè“`‚¤‚±‚ئ‚à‚ ‚é‚ھپAƒ|ƒP
ƒbƒg‚ةژè‚ً“ث‚ءچ‚ٌ‚إŒ©‚ؤ‚¢‚邾‚¯‚ج‚ظ‚¤‚ھ‘½‚¢پBچ،–é‚ج“ç‚ح–ىچط‚©‚çںّ
‚فڈo‚½‚³‚ç‚è‚ئ‚µ‚½ژ‰‹C‚ج‚ب‚¢ƒXپ[ƒv‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@–é’ق‚è‚à’ق‚ê‚ب‚©‚ء‚½پB‹C—ح‚ھ‚ب‚©‚ء‚½پB’‹ٹش‚©‚ç’ق‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إپA–é
‚à‘ت–ع‚¾‚낤‚ئ’ْ‚ك‚ج‹Cژ‚؟‚ھˆأ‰_‚ج‚و‚¤‚ةچL‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB–é‚ح’ق‚邼پA‚»
‚¤ٹو’£‚ء‚ؤ‚à‚¢‚¢‚ح‚¸‚¾‚ھپA‹†‹ة‚جژhگg‚ًژہŒ»‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½ƒVƒ‡ƒbƒN‚ھ‹؟‚¢
‚ؤ‚¢‚½پB‚ي‚½‚µ‚ح‘پپX‚ةƒLƒƒƒrƒ“‚إ–°‚è‚ةڈA‚¢‚½پBگ”ژٹشŒo‚ء‚ؤ‚©‚ê‚ھ‚ي‚½
‚µ‚ج‰،‚إگQ‘ـ‚ة‚‚é‚ـ‚éپB
‚à‘ت–ع‚¾‚낤‚ئ’ْ‚ك‚ج‹Cژ‚؟‚ھˆأ‰_‚ج‚و‚¤‚ةچL‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB–é‚ح’ق‚邼پA‚»
‚¤ٹو’£‚ء‚ؤ‚à‚¢‚¢‚ح‚¸‚¾‚ھپA‹†‹ة‚جژhگg‚ًژہŒ»‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½ƒVƒ‡ƒbƒN‚ھ‹؟‚¢
‚ؤ‚¢‚½پB‚ي‚½‚µ‚ح‘پپX‚ةƒLƒƒƒrƒ“‚إ–°‚è‚ةڈA‚¢‚½پBگ”ژٹشŒo‚ء‚ؤ‚©‚ê‚ھ‚ي‚½
‚µ‚ج‰،‚إگQ‘ـ‚ة‚‚é‚ـ‚éپB
پu’ق‚ꂽ‚ پv
پu‚؛‚ٌ‚؛‚ٌپv
’ل‚¢گ؛‚ھ•ش‚ء‚ؤ‚«‚½پB‚»‚ê‚ء‚«‚è‰ïکb‚ح‘±‚©‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@‚ئ‚±‚ë‚إ•rƒrپ[ƒ‹‚ح—[گH‚ج“ç‚ج‚ئ‚«‚ةٹ£”t‚إˆù‚ٌ‚¾پB‚ـ‚ پA‚±‚ê‚ح‚±‚ê‚إ
‚¤‚ـ‚©‚ء‚½پB
‚¤‚ـ‚©‚ء‚½پB
پ@-•ْپ@—¬-
پ@‚ي‚½‚µ‚ح‰a‚ھ—]‚ê‚خگ¶‚«’·‚炦‚é‚ئژv‚ي‚ê‚éڈêڈٹ‚ةٹز‚µ‚ؤ‚ ‚°‚邱‚ئ‚ة‚µ
‚ؤ‚¢‚éپBƒSƒJƒC‚ب‚ç’ھ‚ھˆّ‚¢‚½ٹâڈê‚â“Dچ»’n‚ةپAƒ‚ƒGƒr‚ح’r‚âگى‚ةپA‚ئ‚¢‚ء
‚½‹ïچ‡‚¾پB“¦‚ھ‚·‚ئ‚«پA‚ي‚½‚µ‚ح‚¢‚آ‚àڈ¬گ؛‚إŒ¾‚¤پB
‚ؤ‚¢‚éپBƒSƒJƒC‚ب‚ç’ھ‚ھˆّ‚¢‚½ٹâڈê‚â“Dچ»’n‚ةپAƒ‚ƒGƒr‚ح’r‚âگى‚ةپA‚ئ‚¢‚ء
‚½‹ïچ‡‚¾پB“¦‚ھ‚·‚ئ‚«پA‚ي‚½‚µ‚ح‚¢‚آ‚àڈ¬گ؛‚إŒ¾‚¤پB
پu‚ب‚ٌ‚ئƒ‰ƒbƒLپ[‚ب‰a‚½‚؟‚وپv
‚ئپB
پ@‘Sچ‘‚ة‚ ‚é’ق‹ï“X‚ج‚ب‚©‚إپA‚ي‚½‚µ‚جچs‚«‚آ‚¯‚ج’ق‹ï“X‚ة‰µ‚³‚êپA‰½•S
گl‚à‚ج‹q‚ج‚ب‚©‚إ‚ي‚½‚µ‚©‚甃‚ي‚êپA‚«‚ه‚¤ˆê“ْ‚ً‰a‚ئ‚µ‚ؤ‚آ‚©‚فڈم‚°‚ç‚ê
‚邱‚ئ‚©‚瓦‚êپA‰a” ‚ج‚ب‚©‚إژم‚炸پA‚»‚µ‚ؤٹC‚â’r‚ة•ْ‚½‚ê‚éپBگlٹش‚ة—ل
‚¦‚é‚ب‚çپA2‰‰~‚ج•َ‚‚¶‚ة“–‚é‚ظ‚اƒ‰ƒbƒLپ[‚بپA‚ ‚é‚¢‚حگيڈê‚إ“G‚ھڈe‚ًŒü
‚¯‘_‚¢‚ًگں‚ـ‚µپAˆّ‚«‹à‚ًˆّ‚±‚¤‚ئ‚µ‚½ڈuٹشپAڈIگي‚ئ‚ب‚ء‚½پA“¯‚¶–½ڈE‚¢‚إ‚à
گ_‚ھ‚©‚è“I‚ةچK‰^‚ئŒ¾‚¤‚ظ‚©‚ب‚¢‚ظ‚اƒcƒC‚ؤ‚¢‚é‰a‚½‚؟‚¾پB
گl‚à‚ج‹q‚ج‚ب‚©‚إ‚ي‚½‚µ‚©‚甃‚ي‚êپA‚«‚ه‚¤ˆê“ْ‚ً‰a‚ئ‚µ‚ؤ‚آ‚©‚فڈم‚°‚ç‚ê
‚邱‚ئ‚©‚瓦‚êپA‰a” ‚ج‚ب‚©‚إژم‚炸پA‚»‚µ‚ؤٹC‚â’r‚ة•ْ‚½‚ê‚éپBگlٹش‚ة—ل
‚¦‚é‚ب‚çپA2‰‰~‚ج•َ‚‚¶‚ة“–‚é‚ظ‚اƒ‰ƒbƒLپ[‚بپA‚ ‚é‚¢‚حگيڈê‚إ“G‚ھڈe‚ًŒü
‚¯‘_‚¢‚ًگں‚ـ‚µپAˆّ‚«‹à‚ًˆّ‚±‚¤‚ئ‚µ‚½ڈuٹشپAڈIگي‚ئ‚ب‚ء‚½پA“¯‚¶–½ڈE‚¢‚إ‚à
گ_‚ھ‚©‚è“I‚ةچK‰^‚ئŒ¾‚¤‚ظ‚©‚ب‚¢‚ظ‚اƒcƒC‚ؤ‚¢‚é‰a‚½‚؟‚¾پB
پ@ƒSƒJƒC‚ً“¦‚ھ‚·‚ج‚ةڈêڈٹ‚حچ¢‚ç‚ب‚¢پB–ع‚ج‘O‚حٹC‚ب‚ج‚¾‚©‚çپB‚µ‚©‚µ’Wگ…
‚جƒGƒr—ق‚ح‚؟‚ه‚ء‚ئ–ï‰î‚إ‚ ‚éپBٹC‚©‚çژ©‘î‚ـ‚إ‚ج‚ ‚¢‚¾‚ة’r‚âگى‚ھ‚ب‚¢
‚±‚ئ‚ھ‘½‚¢پB‚ ‚ء‚ؤ‚àٹٌ‚蓹‚ة‚ب‚ء‚½‚èپA‹A‘î‚ً‹}‚¢‚إ‚¢‚é‚ئ‚«‚à‚ ‚éپBŒ‹‹ا
ژ©‘î‚ـ‚إژ‚ء‚ؤ‹A‚邱‚ئ‚ة‚ب‚é‚ھپA‚±‚ê‚ح‘ه•د‚بچى‹ئ‚ھچT‚¦‚ؤ‚¢‚éپB‚ف‚·‚ف
‚·Œ©ژE‚µ‚ة‚·‚é‚ي‚¯‚ة‚ح‚¢‚©‚ب‚¢پB
‚جƒGƒr—ق‚ح‚؟‚ه‚ء‚ئ–ï‰î‚إ‚ ‚éپBٹC‚©‚çژ©‘î‚ـ‚إ‚ج‚ ‚¢‚¾‚ة’r‚âگى‚ھ‚ب‚¢
‚±‚ئ‚ھ‘½‚¢پB‚ ‚ء‚ؤ‚àٹٌ‚蓹‚ة‚ب‚ء‚½‚èپA‹A‘î‚ً‹}‚¢‚إ‚¢‚é‚ئ‚«‚à‚ ‚éپBŒ‹‹ا
ژ©‘î‚ـ‚إژ‚ء‚ؤ‹A‚邱‚ئ‚ة‚ب‚é‚ھپA‚±‚ê‚ح‘ه•د‚بچى‹ئ‚ھچT‚¦‚ؤ‚¢‚éپB‚ف‚·‚ف
‚·Œ©ژE‚µ‚ة‚·‚é‚ي‚¯‚ة‚ح‚¢‚©‚ب‚¢پB
پ@‚ي‚½‚µ‚حگ…‘…‚إژ”‚¤‚±‚ئ‚ًŒˆ‚كپAگ…‘…‚âƒGƒAپ[ƒ|ƒ“ƒvپAگ…‘گ‚â•~گخ‚ب‚ا”ƒ
‚¢‘µ‚¦‚½پBگ…“¹گ…‚ً’£‚ء‚ؤƒJƒ‹ƒL‚ً”²‚‚½‚ك‚ةگ”ژٹش•ْ’u‚µ‚½پBƒ‚ƒGƒr‚حگ…
‰·‚ج•د‰»‚ة‚ح‹‚¢‚ھگ…ژ؟‚ة•qٹ´‚¾پB‰a‚ح‚ب‚ٌ‚إ‚àگH‚ׂ邩‚çپA—^‚¦‚·‚¬‚ب
‚¢‚و‚¤’چˆس‚³‚¦‚·‚ê‚خ‘‚â‚·‚±‚ئ‚à‰آ”\‚¾پB—^‚¦‚·‚¬‚ھ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ج‚حپAƒ‚ƒG
ƒr‚ھ‹à‹›‚ج‚و‚¤‚ةگH‚׉ك‚¬‚é‚©‚ç‚إ‚ح‚ب‚¢پB—]‚ء‚½‰a‚ھگ…’†‚إ•…”s‚µگ…ژ؟
‚ًˆ«‰»‚³‚¹‚éپB
‚¢‘µ‚¦‚½پBگ…“¹گ…‚ً’£‚ء‚ؤƒJƒ‹ƒL‚ً”²‚‚½‚ك‚ةگ”ژٹش•ْ’u‚µ‚½پBƒ‚ƒGƒr‚حگ…
‰·‚ج•د‰»‚ة‚ح‹‚¢‚ھگ…ژ؟‚ة•qٹ´‚¾پB‰a‚ح‚ب‚ٌ‚إ‚àگH‚ׂ邩‚çپA—^‚¦‚·‚¬‚ب
‚¢‚و‚¤’چˆس‚³‚¦‚·‚ê‚خ‘‚â‚·‚±‚ئ‚à‰آ”\‚¾پB—^‚¦‚·‚¬‚ھ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ج‚حپAƒ‚ƒG
ƒr‚ھ‹à‹›‚ج‚و‚¤‚ةگH‚׉ك‚¬‚é‚©‚ç‚إ‚ح‚ب‚¢پB—]‚ء‚½‰a‚ھگ…’†‚إ•…”s‚µگ…ژ؟
‚ًˆ«‰»‚³‚¹‚éپB
پ@ƒ‚ƒGƒr‚ح‚¢‚آ‚àگ…‘گ‚ة—h‚ç‚êپA”L‚ھکr‚إٹç‚ً‘U‚¤‚و‚¤‚ة’·‚¢•E‚ًژ©–‚·‚é
‚©‚ج‚و‚¤‚ةپA—¼کr‚ًŒًŒف‚ةژg‚¢‚ب‚ھ‚ç‘U‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚ن‚إ—‘‚ج‰©–،‚àچD•¨‚إ
‰©–،‚ًگH‚ׂé‚ئˆف‚ھ‰©گF‚ة“§‚¯‚ؤŒ©‚¦‚éپB’‡ٹش“¯ژm‚ھ”«‰ï‚¤‚ئپAŒف‚¢‚ة‚ز
‚م‚ٌ‚ئ‚ج‚¯‚¼‚é‚ج‚ھˆ¥ژA‚جژd•û‚¾پB‚»‚µ‚ؤ‚ي‚½‚µ‚ج’ق‚è‚ھƒپƒoƒ‹‚©‚çƒ`ƒk’ق
‚è‚ة•د‚é”~‰J“ü‚è‚ج‚±‚ëپA‚¨• ‚¢‚ء‚د‚¢‚ة—‘‚ًژ‚آپB
‚©‚ج‚و‚¤‚ةپA—¼کr‚ًŒًŒف‚ةژg‚¢‚ب‚ھ‚ç‘U‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚ن‚إ—‘‚ج‰©–،‚àچD•¨‚إ
‰©–،‚ًگH‚ׂé‚ئˆف‚ھ‰©گF‚ة“§‚¯‚ؤŒ©‚¦‚éپB’‡ٹش“¯ژm‚ھ”«‰ï‚¤‚ئپAŒف‚¢‚ة‚ز
‚م‚ٌ‚ئ‚ج‚¯‚¼‚é‚ج‚ھˆ¥ژA‚جژd•û‚¾پB‚»‚µ‚ؤ‚ي‚½‚µ‚ج’ق‚è‚ھƒپƒoƒ‹‚©‚çƒ`ƒk’ق
‚è‚ة•د‚é”~‰J“ü‚è‚ج‚±‚ëپA‚¨• ‚¢‚ء‚د‚¢‚ة—‘‚ًژ‚آپB
پ@—]‚ء‚ؤ‚ح“ü‚êپA‚ـ‚½—]‚ء‚ؤ‚حگV“ü‚è‚ً‘‚₵‚ؤ‚¢‚邤‚؟‚ةپAگ…‘…‚حƒ‚ƒGƒr
‚إ“ِ‚â‚©‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚½پB‚ي‚½‚µ‚ح‚·‚ء‚©‚胂ƒGƒr‚ج•\ڈî‚ةˆ¤’…‚ًٹ´‚¶‚ؤ‚¢
‚éپB‚à‚¤پA’ق‚è‰a‚ةچؤ—ک—p‚·‚é‚ب‚ٌ‚ؤ‚±‚ئ‚حگl“¹ڈم‚إ‚«‚ب‚¢پB
‚إ“ِ‚â‚©‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚½پB‚ي‚½‚µ‚ح‚·‚ء‚©‚胂ƒGƒr‚ج•\ڈî‚ةˆ¤’…‚ًٹ´‚¶‚ؤ‚¢
‚éپB‚à‚¤پA’ق‚è‰a‚ةچؤ—ک—p‚·‚é‚ب‚ٌ‚ؤ‚±‚ئ‚حگl“¹ڈم‚إ‚«‚ب‚¢پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

پ@-“V‹C—\‘ھ-
پ@‚¢‚آ”~‰J“ü‚肵‚½‚ج‚©‚ي‚©‚ç‚ب‚¢‚ھپAکA“ْ‚جچ~‰J‚إ‚ ‚éپB‹Cڈغ’،‚ھ”~‰J
“ü‚èگ錾‚ًڈo‚µ‚ؤ‚àڈo‚³‚ب‚‚ؤ‚àپAژP‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚ؤ‚à‚¢‚ب‚‚ؤ‚àپA‰J‚حچ~‚肽
‚¢‚ئ‚«‚ةچ~‚é‚à‚ج‚¾پB‹ك”N‚ح‚ ‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤپuپ–پ–’n•û‚ح‚¢‚آ”~‰J“ü‚肵‚½–ح
—l‚إ‚ ‚éپv‚ئگ錾‚ھ‚ ‚éپB‚¶‚ء‚ئ‚و‚¤‚·‚ً‚ف‚ؤ‚¢‚ؤپA‚ـ‚؟‚ھ‚¢‚ب‚¢‚ئ”»’f‚µ‚ؤ
‚ج‚±‚ئ‚¾‚낤‚ھپA‚ ‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ج‚±‚ئ‚¾‚©‚ç’P‚ب‚é•ٌچگ‚إˆس–،‚ًژ‚½‚ب‚¢پB‹C
ڈغ‰qگ¯‚àƒŒپ[ƒ_پ[ژg‚ي‚¸‚ة‚¾‚ê‚ة‚¾‚ء‚ؤ‚إ‚«‚邱‚ئ‚¾پB‚¾‚¢‚½‚¢‚»‚ج‚±‚ë‚ة
‚ب‚ê‚خپA‘fگl‚ج‚ي‚½‚µ‚ة‚¾‚ء‚ؤپu”~‰J‚ة“ü‚ء‚½‚بپv‚ئ‚ي‚©‚éپB
“ü‚èگ錾‚ًڈo‚µ‚ؤ‚àڈo‚³‚ب‚‚ؤ‚àپAژP‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚ؤ‚à‚¢‚ب‚‚ؤ‚àپA‰J‚حچ~‚肽
‚¢‚ئ‚«‚ةچ~‚é‚à‚ج‚¾پB‹ك”N‚ح‚ ‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤپuپ–پ–’n•û‚ح‚¢‚آ”~‰J“ü‚肵‚½–ح
—l‚إ‚ ‚éپv‚ئگ錾‚ھ‚ ‚éپB‚¶‚ء‚ئ‚و‚¤‚·‚ً‚ف‚ؤ‚¢‚ؤپA‚ـ‚؟‚ھ‚¢‚ب‚¢‚ئ”»’f‚µ‚ؤ
‚ج‚±‚ئ‚¾‚낤‚ھپA‚ ‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ج‚±‚ئ‚¾‚©‚ç’P‚ب‚é•ٌچگ‚إˆس–،‚ًژ‚½‚ب‚¢پB‹C
ڈغ‰qگ¯‚àƒŒپ[ƒ_پ[ژg‚ي‚¸‚ة‚¾‚ê‚ة‚¾‚ء‚ؤ‚إ‚«‚邱‚ئ‚¾پB‚¾‚¢‚½‚¢‚»‚ج‚±‚ë‚ة
‚ب‚ê‚خپA‘fگl‚ج‚ي‚½‚µ‚ة‚¾‚ء‚ؤپu”~‰J‚ة“ü‚ء‚½‚بپv‚ئ‚ي‚©‚éپB
پ@”~‰J“ü‚èگ錾‚ً‚·‚é‚ئ”ç“÷‚ج‚و‚¤‚ة“ٌپAژO“ْ‚حگ°“V‚ھ‘±‚«پA”~‰J–¾‚¯گé
Œ¾‚ھ‚ ‚é‚ئ“ٌپAژO“ْ‚حچ~‚葱‚‚à‚ج‚¾پB‚»‚¤‚¢‚¤گhژ_‚ًنr‚ك‚½‚‚ب‚¢‚ج‚إپA‚
‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤگ錾‚ً‚·‚é–¼ˆؤ‚ًژv‚¢•t‚¢‚½‚ج‚¾پB
Œ¾‚ھ‚ ‚é‚ئ“ٌپAژO“ْ‚حچ~‚葱‚‚à‚ج‚¾پB‚»‚¤‚¢‚¤گhژ_‚ًنr‚ك‚½‚‚ب‚¢‚ج‚إپA‚
‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤگ錾‚ً‚·‚é–¼ˆؤ‚ًژv‚¢•t‚¢‚½‚ج‚¾پB
پ@‚»‚¤‚¢‚¤ژè–@‚ھ‚ـ‚©‚è’ت‚é‚ب‚çپA–¾“ْ‚ج“V‹C—\•ٌ‚à–¾“ْ‚ج–é‚ة‚·‚ê‚خ‚¢
‚¢پBپu‚«‚ه‚¤‚ح‘Sچ‘“I‚ةگ°‚ꂽ–ح—l‚إ‚·پvپu‚«‚ه‚¤‚ح“Œ–k’n•ûپAپ–پ–‘؛‚ة‹Gگك
ٹO‚ê‚جگل‚ھچ~‚è‚ـ‚µ‚½پv‚ئپB•·‚‘¤‚àپu‚»‚¤‚¾‚ء‚½‚ج‚©پv‚ئگ^ژہ–،‚ً‘ر‚ر‚ؤژَ‚¯
ژو‚ê‚éپB‚à‚ء‚ئ‚·‚²‚¢—ک“_‚ح‹Cڈغ’،‚جگEˆُ‚ھ“ٌپAژOگl‚إ‚±‚ئ‘«‚è‘ه•‚بچ‘
گإ‚جگكŒ¸‚ئ‚ب‚éپB‚»‚ج•ھ‚ًکVگlˆم—أ”ï‚ة‰ٌ‚µپA10پ“‚à20پ“‚à•‰’S‚ھŒy‚‚ب‚é
‚ئ‚µ‚½‚çپA‚ي‚½‚µ‚ح‚±‚±‚إ‰وٹْ“I‚ب’ٌˆؤ‚ً‚µ‚½‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB
‚¢پBپu‚«‚ه‚¤‚ح‘Sچ‘“I‚ةگ°‚ꂽ–ح—l‚إ‚·پvپu‚«‚ه‚¤‚ح“Œ–k’n•ûپAپ–پ–‘؛‚ة‹Gگك
ٹO‚ê‚جگل‚ھچ~‚è‚ـ‚µ‚½پv‚ئپB•·‚‘¤‚àپu‚»‚¤‚¾‚ء‚½‚ج‚©پv‚ئگ^ژہ–،‚ً‘ر‚ر‚ؤژَ‚¯
ژو‚ê‚éپB‚à‚ء‚ئ‚·‚²‚¢—ک“_‚ح‹Cڈغ’،‚جگEˆُ‚ھ“ٌپAژOگl‚إ‚±‚ئ‘«‚è‘ه•‚بچ‘
گإ‚جگكŒ¸‚ئ‚ب‚éپB‚»‚ج•ھ‚ًکVگlˆم—أ”ï‚ة‰ٌ‚µپA10پ“‚à20پ“‚à•‰’S‚ھŒy‚‚ب‚é
‚ئ‚µ‚½‚çپA‚ي‚½‚µ‚ح‚±‚±‚إ‰وٹْ“I‚ب’ٌˆؤ‚ً‚µ‚½‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB
پ@‚ئ‚حŒ¾‚¦پA’©ٹ§‚ً‚ك‚‚ء‚ؤ‚ـ‚¸–ع‚ً’ت‚·‚ج‚ح‚«‚ه‚¤‚ج“VŒَ‚إ‚ ‚éپB‰œ‚³‚ـ•û
‚حگô‘َ•¨‚ًٹ±‚µ‚ؤٹOڈo‚إ‚«‚é‚©پA‰ش’d‚جگ…‚â‚è‚حڈب‚¯‚é‚©پA—L—ح‚بژvˆؤچق
—؟‚¾پB
‚حگô‘َ•¨‚ًٹ±‚µ‚ؤٹOڈo‚إ‚«‚é‚©پA‰ش’d‚جگ…‚â‚è‚حڈب‚¯‚é‚©پA—L—ح‚بژvˆؤچق
—؟‚¾پB
پ@“V‹C—\•ٌ‚ھ‚¢‚ـ‚¾“V‹C—\‘ھ‚جˆو‚إ‚ ‚ء‚ؤ“–‚½‚ç‚ب‚¢‚ج‚حپA‚à‚ء‚ئگإ‹à‚ً
“ٹ“ü‚µ‚ؤ‹@ٹي‚جٹJ”‚âگ¸“x‚جچ‚‚¢‰qگ¯‚ًڈم‚°‚é•K—v‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚©پB
•ھگحٹ¯‚جگlگ”‚àŒ¤ڈC‚à‘«‚è‚ب‚¢‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB‚±‚ج‚و‚¤‚ةڈ‚µ‚ح‹Cڈغ’،
‚ة“¯ڈî‚à‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚©‚çپAگج‚ا‚¨‚èپA‚«‚؟‚ٌ‚ئ”~‰J“ü‚èگ錾‚à”~‰J–¾‚¯گé
Œ¾‚àژ©گM‚ً‚à‚ء‚ؤ‚â‚ء‚ؤ‚ظ‚µ‚¢پB‚»‚µ‚ؤ—\•ٌ‚ھ“–‚½‚ç‚ب‚©‚ء‚½—[چڈ‚ة‚حپu‚·
‚ف‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پv‚جˆêŒ¾‚‚ç‚¢‚ ‚ء‚ؤ‚µ‚©‚é‚ׂ«‚¾پB
“ٹ“ü‚µ‚ؤ‹@ٹي‚جٹJ”‚âگ¸“x‚جچ‚‚¢‰qگ¯‚ًڈم‚°‚é•K—v‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚©پB
•ھگحٹ¯‚جگlگ”‚àŒ¤ڈC‚à‘«‚è‚ب‚¢‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB‚±‚ج‚و‚¤‚ةڈ‚µ‚ح‹Cڈغ’،
‚ة“¯ڈî‚à‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚©‚çپAگج‚ا‚¨‚èپA‚«‚؟‚ٌ‚ئ”~‰J“ü‚èگ錾‚à”~‰J–¾‚¯گé
Œ¾‚àژ©گM‚ً‚à‚ء‚ؤ‚â‚ء‚ؤ‚ظ‚µ‚¢پB‚»‚µ‚ؤ—\•ٌ‚ھ“–‚½‚ç‚ب‚©‚ء‚½—[چڈ‚ة‚حپu‚·
‚ف‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پv‚جˆêŒ¾‚‚ç‚¢‚ ‚ء‚ؤ‚µ‚©‚é‚ׂ«‚¾پB
پ@‚»‚à‚»‚àپu—\•ٌپi—\‚ك•ٌ‚¶‚éپjپv‚ئڈج‚µپAŒِڈO‚ج“d”g‚ًژg‚ء‚ؤ“°پX‚ئ‰R‚ھŒ¾‚¦
‚é‚ج‚ح‹Cڈغ’،‚‚ç‚¢‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBپu“V‹C—\•ٌپv‚ً‰üڈج‚µپu“V‹C—\‘ھپv‚ئ‚·‚×
‚«‚¾‚낤پB
‚é‚ج‚ح‹Cڈغ’،‚‚ç‚¢‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBپu“V‹C—\•ٌپv‚ً‰üڈج‚µپu“V‹C—\‘ھپv‚ئ‚·‚×
‚«‚¾‚낤پB
پ@’ق‚è‚ةچs‚¯‚ت‹x“ْپB”~‰J‹َ‚ً’‚ك‚ب‚ھ‚çپA‚±‚ê‚ح‚آ‚ـ‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًچl‚¦‚ؤ
‚¢‚é•”—ق‚ة“ü‚é‚ج‚¾‚낤‚©پB
‚¢‚é•”—ق‚ة“ü‚é‚ج‚¾‚낤‚©پB

پ@پ|‹ضپ@‹هپ|
پ@چD“V–³•—پB
’r‚ج‚و‚¤‚ةگأ‚©‚بٹCپB
پuچ،‚جژٹْ‚ة‚±‚ٌ‚ب“ْ‚ح’؟‚µ‚¢پv
ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ة“’…‚µپA‘و‚P“ٹ‚ًچد‚ـ‚¹‚½‚l‚³‚ٌ‚ھŒ¾‚ء‚½پB
ٹm‚©‚ة‚±‚ٌ‚ب‚ة‰¸‚â‚©‚بٹCڈم‚ح–إ‘½‚ة‚ب‚¢پB
‚·‚®‚ة–hٹ¦’…‚ً’E‚¢‚¾پB
پu‚ج‚ٌ‚ر‚è‚â‚ب‚ پB‚¢‚¢“ْ‚âپB’ق‚ê‚ٌ‚إ‚à‚¢‚¢پBٹئ‚ًڈo‚µ‚ؤ‚¢‚邾‚¯‚إ–‘«
‚âپv
‚âپv
‚»‚ê‚ھٹC’ê‚ة“`‚ي‚ء‚½‚ج‚©پA‚»‚ج“ْ‚حƒsƒNƒٹ‚ئ‚à‚µ‚ب‚©‚ء‚½پB
‚آ‚ـ‚è‚P•C‚à’ق‚ê‚ب‚©‚ء‚½پB
ˆبŒمپAپu’ق‚ê‚ٌ‚إ‚à‚¢‚¢پv‚ح‹ض‹ه‚ئگ\‚µچ‡‚ي‚¹‚½پB
پ@پ|ژلپ@’ھپ|
پ@‹x“ْ‚ح‚¢‚آ‚àŒˆ‚ـ‚ء‚½’‡ٹش‚ئ‘D’ق‚肾پB
پ@ٹOٹC‚©‚ç”g‚ً‰ں‚·‚و‚¤‚ةگپ‚«•t‚¯‚é“ىٹٌ‚è‚ج•—‚ح‚¶‚«ژ،‚ـ‚ء‚½‚à‚ج‚جپAƒA
ƒ^ƒٹ‚ئ‚¢‚¦‚خƒLƒX‚©ƒAƒ‰ƒJƒu‚جڈ¬‚³‚ب‚à‚ج‚炵‚‰a‚ًژو‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢پB‚ي
‚½‚µ‚جژdٹ|‚¯‚حƒLƒX‚جŒû‚ةچ‡‚¤‚و‚¤‚بڈ¬‚³‚ب‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA40cm‚©‚ç50cm
‚جچ•‘â‚ةڈئڈ€‚ًچ‡‚ي‚¹‚½‚à‚ج‚ب‚ج‚¾پB‘¼‚ج‘D‚حƒAƒW‚ً’ق‚邾‚¯‚جژdٹ|‚¯
‚ھ‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚إپAƒLƒX‚ب‚ا‚جƒAƒ^ƒٹ‚à‚ب‚پA‚½‚¾پA‘ز‚؟‚ج‘ق‹ü‚بژٹش‚ًژ‚ؤ—]‚µ
‚ؤ‚¢‚éپB
ƒ^ƒٹ‚ئ‚¢‚¦‚خƒLƒX‚©ƒAƒ‰ƒJƒu‚جڈ¬‚³‚ب‚à‚ج‚炵‚‰a‚ًژو‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢پB‚ي
‚½‚µ‚جژdٹ|‚¯‚حƒLƒX‚جŒû‚ةچ‡‚¤‚و‚¤‚بڈ¬‚³‚ب‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA40cm‚©‚ç50cm
‚جچ•‘â‚ةڈئڈ€‚ًچ‡‚ي‚¹‚½‚à‚ج‚ب‚ج‚¾پB‘¼‚ج‘D‚حƒAƒW‚ً’ق‚邾‚¯‚جژdٹ|‚¯
‚ھ‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚إپAƒLƒX‚ب‚ا‚جƒAƒ^ƒٹ‚à‚ب‚پA‚½‚¾پA‘ز‚؟‚ج‘ق‹ü‚بژٹش‚ًژ‚ؤ—]‚µ
‚ؤ‚¢‚éپB
پ@ƒAƒW’ق‚è‚جƒTƒrƒLگj‚ج‰؛‚ةƒeƒ“ƒrƒ“‚ً•t‚¯پA‚»‚±‚©‚çچ•‘â—p‚جگj‚ًڈo‚µپA
ƒAƒW‚¾‚¯‚إ‚ب‚پAƒJƒڈƒnƒMپAƒپƒoƒ‹پA‘â‚âƒAƒ‰ƒJƒu‚ب‚ا‚ج’ꕨ‚à“¯ژ‚ة‘_‚¦‚é
‚و‚¤‚ة‚µ‚½‚ج‚ھ‚ي‚½‚µ‚جژdٹ|‚¯‚¾پB
ƒAƒW‚¾‚¯‚إ‚ب‚پAƒJƒڈƒnƒMپAƒپƒoƒ‹پA‘â‚âƒAƒ‰ƒJƒu‚ب‚ا‚ج’ꕨ‚à“¯ژ‚ة‘_‚¦‚é
‚و‚¤‚ة‚µ‚½‚ج‚ھ‚ي‚½‚µ‚جژdٹ|‚¯‚¾پB
پ@گh•ّ‚ھ‚«‚©‚¸‹›’T‚ً”`‚«چ‚ف‚ب‚ھ‚çƒ|ƒCƒ“ƒg‚ًˆع“®‚·‚é‘D‚ھ‘‚¦‚ؤ‚‚éپB
‚ي‚½‚µ‚ج‘D‹ك‚‚©‚牓‚´‚©‚é‘D‚à‚ ‚èپA‚ـ‚½‹كٹٌ‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ“ٹ•d‚·‚é‘D‚à‚¢
‚éپB‚ي‚½‚µ‚ح“®‚©‚ب‚¢پB‚±‚±‚ھˆê”ش‚¢‚¢ƒ|ƒCƒ“ƒg‚¾‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ً’m‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚±
‚±‚إ‚¾‚ك‚ب‚ç‚ا‚±‚ضچs‚ء‚ؤ‚à’ق‚ê‚ب‚¢‚ج‚¾پBˆع“®‚·‚é‘D‚ح‹C•ھ“]ٹ·‚ئ‚¢‚¤‚ج
‚ھ‘½‚¢پB‘D’·‚ح“¯‘Dژز‚ة‹C‚ًŒ‚¤‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚ھ—L—؟‚ج’ق‘D‚¾‚ء‚½‚ç
‚ب‚¨‚³‚ç‚ج‚±‚ئ‚¾‚낤پB
‚ي‚½‚µ‚ج‘D‹ك‚‚©‚牓‚´‚©‚é‘D‚à‚ ‚èپA‚ـ‚½‹كٹٌ‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ“ٹ•d‚·‚é‘D‚à‚¢
‚éپB‚ي‚½‚µ‚ح“®‚©‚ب‚¢پB‚±‚±‚ھˆê”ش‚¢‚¢ƒ|ƒCƒ“ƒg‚¾‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ً’m‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚±
‚±‚إ‚¾‚ك‚ب‚ç‚ا‚±‚ضچs‚ء‚ؤ‚à’ق‚ê‚ب‚¢‚ج‚¾پBˆع“®‚·‚é‘D‚ح‹C•ھ“]ٹ·‚ئ‚¢‚¤‚ج
‚ھ‘½‚¢پB‘D’·‚ح“¯‘Dژز‚ة‹C‚ًŒ‚¤‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚ھ—L—؟‚ج’ق‘D‚¾‚ء‚½‚ç
‚ب‚¨‚³‚ç‚ج‚±‚ئ‚¾‚낤پB
پ@“¯چs‚ج•l‚؟‚ل‚ٌ‚حƒLƒX‚âƒAƒ‰ƒJƒu‚ً‚و‚—g‚°‚éپB 

پuƒ`ƒkگjپA‰½چ†پHپv
پu‚Qچ†‚ة‚µ‚ـ‚µ‚½پv
‚ي‚½‚µ‚جگj‚و‚èگ”’iڈ¬‚³‚¢پB
پu‚»‚ꂶ‚ل‚ پAƒ`ƒk‚ھٹ|‚©‚ء‚½‚ئ‚«پA‘خ‰‚إ‚«‚ب‚¢‚وپBگjپAگL‚ر‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚وپv
پu‚إ‚à‚¢‚ë‚¢‚ë’ق‚ء‚½‚ظ‚¤‚ھٹy‚µ‚¢‚إ‚·‚©‚çپv
ٹوŒإ‚بƒ„ƒcپA‚ئژv‚ء‚½‚ئ‚«پA’u‚¢‚ؤ‚¢‚½ٹئ‚ھڈc‚ة‘ه‚«‚ژٌ‚ً‹ب‚°‚½پBگ¨‚¢‚ً
‚آ‚¯‚ؤٹئ‚ًژ‚؟ڈم‚°‚é‚ئ•نگو‚ھپu‚آپv‚جژڑ‚ةٹC–ت‚ة“ث‚ءچ‚فپA‚»‚ê‚ھƒ`ƒk‚إ
‚ ‚邱‚ئ‚ھ’¼ٹ´‚إ‚«‚½پB
‚آ‚¯‚ؤٹئ‚ًژ‚؟ڈم‚°‚é‚ئ•نگو‚ھپu‚آپv‚جژڑ‚ةٹC–ت‚ة“ث‚ءچ‚فپA‚»‚ê‚ھƒ`ƒk‚إ
‚ ‚邱‚ئ‚ھ’¼ٹ´‚إ‚«‚½پB
پuƒ`ƒk‚âپB‚«‚½‚¼‚¨پv
ژv‚ي‚¸‹©‚شپB’ق‚ꂽپA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚و‚è‹©‚ׂéپA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ج‚ظ‚¤‚ھٹً‚µ‚¢پB
پuƒ^ƒ‚ڈo‚µ‚ـ‚µ‚ه‚¤‚©پv
•l‚؟‚ل‚ٌ‚ھگU‚è•ش‚éپBژdٹ|‚¯‚ً‚R‚چ‚ظ‚اٹھ‚«ڈم‚°‚½‚ئ‚±‚ë‚إ
پu‚¢‚âپA‚¢‚¢پBڈ¬‚³‚¢‚ف‚½‚¢پv
‚»‚ê‚حچإڈ‰‚ج’ïچR‚¾‚¯‚إپA‚ ‚ئ‚ح—حگs‚«‚½‚ج‚©ٹy‚ةڈم‚ھ‚ء‚ؤ‚«‚½پBٹC–ت‚©
‚ç‚ذ‚ه‚¢‚ئچط‚ء—t‚إ‚àˆّ‚«”²‚‚و‚¤‚ة‹›‚ًژو‚èچ‚قپB—g‚ء‚ؤ‚«‚½‚ج‚ح23cmپA
ڈ¬گU‚è‚جƒ`ƒkپB‚±‚ج’ِ“x‚ج‚حƒ`ƒk‚ئŒ¾‚ي‚¸پuƒپƒCƒ^پv‚ئ‚¢‚¤•تڈج‚ھ‚ ‚éپBڈ¬‚³‚¢
‚¤‚؟‚ح‘ج‘¤‚ةڈcژب‚ھ‚ ‚èپA‚»‚ê‚ھگجپAژه•w‚ھژg‚ء‚ؤ‚¢‚½گô‘َ”آ‚ج‚و‚¤‚ب–ح
—l‚ةژ—‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚çپA”آ–عپiƒCƒ^ƒپپj‚ھوa‚ء‚ؤƒپƒCƒ^‚ئ‚ب‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤پB‚ة‚¬‚èژُ
ژi‚جƒgƒچ‚¾‚جƒuƒٹ‚¾‚ج‚ًپuƒlƒ^پv‚ئŒ¾‚¤‚ھپAŒ³‚حپuƒ^ƒlپv‚إ‚ ‚ء‚½‚ج‚ً‚ذ‚ء‚‚è•ش
‚µ‚ؤŒؤ‚ش‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚ئ“¯‚¶‚¾پB
‚ç‚ذ‚ه‚¢‚ئچط‚ء—t‚إ‚àˆّ‚«”²‚‚و‚¤‚ة‹›‚ًژو‚èچ‚قپB—g‚ء‚ؤ‚«‚½‚ج‚ح23cmپA
ڈ¬گU‚è‚جƒ`ƒkپB‚±‚ج’ِ“x‚ج‚حƒ`ƒk‚ئŒ¾‚ي‚¸پuƒپƒCƒ^پv‚ئ‚¢‚¤•تڈج‚ھ‚ ‚éپBڈ¬‚³‚¢
‚¤‚؟‚ح‘ج‘¤‚ةڈcژب‚ھ‚ ‚èپA‚»‚ê‚ھگجپAژه•w‚ھژg‚ء‚ؤ‚¢‚½گô‘َ”آ‚ج‚و‚¤‚ب–ح
—l‚ةژ—‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚çپA”آ–عپiƒCƒ^ƒپپj‚ھوa‚ء‚ؤƒپƒCƒ^‚ئ‚ب‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤پB‚ة‚¬‚èژُ
ژi‚جƒgƒچ‚¾‚جƒuƒٹ‚¾‚ج‚ًپuƒlƒ^پv‚ئŒ¾‚¤‚ھپAŒ³‚حپuƒ^ƒlپv‚إ‚ ‚ء‚½‚ج‚ً‚ذ‚ء‚‚è•ش
‚µ‚ؤŒؤ‚ش‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚ئ“¯‚¶‚¾پB
پu‚»‚ê‚‚ç‚¢‚إ‚à‚Qچ†پAگL‚ر‚ـ‚·‚©پv
پuگL‚ر‚ٌ‚¾‚ëپB‚»‚ê‚ة‚«‚ف‚جٹئپA‚و‚‚µ‚ب‚é‚©‚çپv
‚©‚ê‚حˆہگS‚µ‚½‚و‚¤‚ة‚ـ‚½ƒLƒX’ق‚è‚ة‹»‚¶‚ؤ‚¢‚½پB
پuƒAƒW’ق‚è‚ة‚«‚ؤ‚±‚ٌ‚ب‚ةƒAƒW’ق‚ê‚ٌ‚±‚ئ‚à’؟‚µ‚¢‚ب‚ پv
پu‚»‚¤‚إ‚·‚©پv
‘D‚إƒAƒW’ق‚è‚ًژn‚ك‚ؤˆê”N‚àŒo‚½‚ب‚¢‚©‚ê‚ح‚â‚ء‚ئŒ»ژہ‚جŒµ‚µ‚³‚ھ‚ي‚©‚ء
‚½‚و‚¤‚¾‚ء‚½پB
‚½‚و‚¤‚¾‚ء‚½پB
پ@‹A‘îŒمپA‚ـ‚¸‚ي‚½‚µ‚ھ‚·‚邱‚ئ‚ح“ü—پ‚إ‚ ‚éپB‘پ’©‚©‚ç‚ج’ق‚è‚ح‹A‘î‚à‘پ
‚پA–¾‚é‚¢‚¤‚؟‚ج“ü—پ‚ح‹Cژ‚؟‚ج‚¢‚¢‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µ‚ب‚؛’ق‚ê‚ب‚©‚ء‚½
‚ج‚©پA‚ئ‚¢‚¤‹^–â‚ھ“ھ‚ً‚à‚½‚°پA—پژ؛‚ج‚ي‚½‚µ‚ح‚©‚ب‚è“‚¢ٹç‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½
‚ةˆل‚¢‚ب‚¢پB
‚پA–¾‚é‚¢‚¤‚؟‚ج“ü—پ‚ح‹Cژ‚؟‚ج‚¢‚¢‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µ‚ب‚؛’ق‚ê‚ب‚©‚ء‚½
‚ج‚©پA‚ئ‚¢‚¤‹^–â‚ھ“ھ‚ً‚à‚½‚°پA—پژ؛‚ج‚ي‚½‚µ‚ح‚©‚ب‚è“‚¢ٹç‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½
‚ةˆل‚¢‚ب‚¢پB
پ@‚±‚ج“ْ‚حژل’ھپB
پuژل’ھ‚حٹC‚ج’ê‚©‚ç’ھ‚ھ“®‚“ْ‚¶‚ل‚©‚ç’ق‚ê‚ٌ‚ئ‚«‚ھ‘½‚¢پBگlٹش‚إŒ¾‚¤‚½‚ç
ٹآ‹«‚ھ‚¢‚ء‚ط‚ٌ‚إ•د‚ي‚é‚آپ[‚±‚ئ‚¶‚ل‚ë‚©‚بپv
ٹآ‹«‚ھ‚¢‚ء‚ط‚ٌ‚إ•د‚ي‚é‚آپ[‚±‚ئ‚¶‚ل‚ë‚©‚بپv
‚©‚آ‚ؤ‹™ژt‚©‚ç•·‚¢‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚éپBژل’ھ‚ح‹›‚½‚؟‚ةگH—~‚ھ‚ي‚©‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤
‚±‚ئ‚©پB
‚±‚ئ‚©پB
پu’©پAگH‚ي‚ٌ‚â‚ء‚½‚ئ‚«‚ح—[•û‚حگH‚¤پi’ق‚ê‚éپjپB’©پAگH‚¤‚½“ْ‚ح—[•û‚حگH‚ي
‚ٌ‚ب‚ پB‚وپ[‚إ‚«‚؟‚ه‚é‚ب‚ پv
‚ٌ‚ب‚ پB‚وپ[‚إ‚«‚؟‚ه‚é‚ب‚ پv
‚ئ‚à‹™ژt‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚ê‚إ‚حچ،“ْ‚ج—[•û‚ح‚ا‚¤‚¾‚낤‚©پBپu’©گH‚ي‚ٌ‚â
‚ء‚½‚ئ‚«‚حپv‚ًŒںڈط‚µ‚½‚¢‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚½پB
‚ء‚½‚ئ‚«‚حپv‚ًŒںڈط‚µ‚½‚¢‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚½پB
پ@‚ي‚½‚µ‚ھ‚ب‚ة‚©‚ًژv‚¢‚آ‚‚ئپA‚»‚ê‚ح‚و‚¢•ûŒü‚ض‚ا‚ٌ‚ا‚ٌ•‘‚¢ڈم‚ھ‚éپB’Œ
ژŒv‚ح14‚ًژw‚µ‚ؤ‚¢‚éپBٹش‚ةچ‡‚¤پB
ژŒv‚ح14‚ًژw‚µ‚ؤ‚¢‚éپBٹش‚ةچ‡‚¤پB
پ@‚ي‚½‚µ‚ح‚l‚³‚ٌ‚ة“dکb‚ً‚µ‚½پB‚©‚ê‚ح’ق‚è‚حچD‚«‚¾‚ھپAچخ‚جٹ„‚è‚ة‘پ‹N‚«
‚ھ‹êژè‚إ‘پ’©‚Tژڈoچ`‚ج“ْ‚حگ؛‚ًٹ|‚¯‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB
‚ھ‹êژè‚إ‘پ’©‚Tژڈoچ`‚ج“ْ‚حگ؛‚ًٹ|‚¯‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB
پu‚±‚ê‚©‚ç‚ا‚¤‚إ‚·‚©پB’©’ق‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚ٌ‚إپA—[•û‚ح‚¢‚¢‚ٌ‚¶‚ل‚ب‚¢‚©
‚ئپEپEپEپv
‚ئپEپEپEپv
‚ي‚½‚µ‚ح”–•X‚ً“¥‚قژv‚¢‚إگTڈd‚ة—U‚ء‚½پB
پu‚¢‚¢‚ث‚¦پB‰½ژ‚ةچ`‚ة‚·‚éپHپv
پu4ژپi16ژپj‚إ‚حپHپv
پu‚¢‚¢‚وپB—ˆڈT‚حچs‚¯‚ب‚¢‚©‚çچ،ڈTپAچs‚«‚½‚©‚ء‚½‚ٌ‚âپv
Œ_–ٌگ¬—§پB3ژ‚ة‰ئ‚ًڈo‚ê‚خ‚¢‚¢‚©‚çˆêژٹش‚ن‚ء‚‚è‹x‚ٌ‚إ‚¨‚±‚¤پB
پ@—\’è’ت‚è4ژڈ‚µ‰ك‚¬ڈoچ`پB’©‚جƒ|ƒCƒ“ƒg‚ة‚ز‚½‚è‚ئ—¯‚éپB‹C•ھˆêگVپB”و‚ê
‚à‚ب‚¢‚µ•—‚à‚ب‚¢پB‘ه‹™‚ج—\ٹ´پB‚±‚ج‚ئ‚«پA‚l‚³‚ٌ‚ھ‹¶ٹى‚ج‹©‚ر‚ً‚ ‚°‚½پB
‚à‚ب‚¢‚µ•—‚à‚ب‚¢پB‘ه‹™‚ج—\ٹ´پB‚±‚ج‚ئ‚«پA‚l‚³‚ٌ‚ھ‹¶ٹى‚ج‹©‚ر‚ً‚ ‚°‚½پB
پu‚¢‚¢‚ب‚ پBگâچD‚ج’ق‚è“ْکa‚â‚ب‚ پv
پ@ژT‚«‰a‚ًƒAƒ~ƒJƒS‚ة‹l‚كپA—â“€ٹCکV‚ًگj‚ة•t‚¯‚ؤ20‚چ‚جٹC’ê‚ة“ٹ“üپBٹC
’ê‚إ‹›‚ھڈW‚ـ‚ء‚ؤ—ˆ‚é‚و‚¤‚ةژT‚«‰a‚ً‘ه‚«‚گU‚ء‚ؤژU‚ç‚·پBƒAƒW‚â‘â‚âƒپƒo
ƒ‹‚ب‚ا‚ھˆêگؤ‚ة‰a‚ً–عٹ|‚¯‚ؤڈW‚ـ‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚·‚ًکA‘z‚µ‹ظ’£‚·‚éپB
—§‚ء‚½‚ـ‚ـٹئ‚ًˆ¬‚è’÷‚ك‹ظ‹}‘شگ¨‚¾پB
’ê‚إ‹›‚ھڈW‚ـ‚ء‚ؤ—ˆ‚é‚و‚¤‚ةژT‚«‰a‚ً‘ه‚«‚گU‚ء‚ؤژU‚ç‚·پBƒAƒW‚â‘â‚âƒپƒo
ƒ‹‚ب‚ا‚ھˆêگؤ‚ة‰a‚ً–عٹ|‚¯‚ؤڈW‚ـ‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚·‚ًکA‘z‚µ‹ظ’£‚·‚éپB
—§‚ء‚½‚ـ‚ـٹئ‚ًˆ¬‚è’÷‚ك‹ظ‹}‘شگ¨‚¾پB
پ@‘ه‚«‚گU‚ء‚ؤگأژ~پB‚ـ‚½گU‚ء‚ؤ‚حگأژ~پB‘پ‰ك‚¬‚ؤ‚à‚ج‚ٌ‚ر‚肵‚ؤ‚¢‚ؤ‚à‚¢‚¯
‚ب‚¢پB‚»‚جƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO‚±‚»‚ھ’ق‰ت‚ً•ھ‚¯‚éپBگ”‰ٌŒJ‚è•ش‚µ‹l‚ك‚½‰a‚ھ‚ب‚‚ب‚é
‚ئٹھ‚«ڈم‚°‚éپB‚ب‚‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚حگU‚é‚ئ‚«‚جگ…‚ج’ïچRپAڈd‚³‚إٹ´‚¶ژو‚ê‚éپB‚ـ
‚½‹l‚ك‚ؤ“ٹ“üپBگU‚éپBگأژ~‚µگ_Œo‚ً•نگو‚ةڈW’†پB‚Pژٹش‚àŒJ‚è•ش‚µ‚½‹“‹هپA
‹›‚©‚ç‚ب‚ٌ‚ج‰¹چ¹‘؟‚à‚ب‚¢پB‘ه‹™‚ج—\ٹ´‚حŒك‘O‚ةˆّ‚«‘±‚«گâ–]‚ض‚ج—\ٹ´
‚ة•د‚ي‚éپB
‚ب‚¢پB‚»‚جƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO‚±‚»‚ھ’ق‰ت‚ً•ھ‚¯‚éپBگ”‰ٌŒJ‚è•ش‚µ‹l‚ك‚½‰a‚ھ‚ب‚‚ب‚é
‚ئٹھ‚«ڈم‚°‚éپB‚ب‚‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚حگU‚é‚ئ‚«‚جگ…‚ج’ïچRپAڈd‚³‚إٹ´‚¶ژو‚ê‚éپB‚ـ
‚½‹l‚ك‚ؤ“ٹ“üپBگU‚éپBگأژ~‚µگ_Œo‚ً•نگو‚ةڈW’†پB‚Pژٹش‚àŒJ‚è•ش‚µ‚½‹“‹هپA
‹›‚©‚ç‚ب‚ٌ‚ج‰¹چ¹‘؟‚à‚ب‚¢پB‘ه‹™‚ج—\ٹ´‚حŒك‘O‚ةˆّ‚«‘±‚«گâ–]‚ض‚ج—\ٹ´
‚ة•د‚ي‚éپB
پu‚â‚ء‚دپAژل’ھ‚ء‚ؤ‚ج‚ھ‚¢‚©‚ٌ‚ج‚â‚ë‚©پv
‹l‚ك‚éژè‚ً‹x‚كٹَ–]‚ًژ¸‚ء‚½گ؛‚إ‚l‚³‚ٌ‚ةŒ¾‚¤پB
پuچ،‚©‚ç‚âپBˆأ‚‚ب‚éگ،‘O‚ة‚ح—ˆ‚éپB‘ه‚«‚¢‚ج‚ھ—ˆ‚éپv
‚©‚ê‚حŒك‘O’†‚ً’m‚ç‚ب‚¢‚©‚çگ¸گ_—ح‚ھ‚ ‚éپBپu’©گH‚ي‚ٌ‚â‚ء‚½‚ç—[پv‚»‚ê‚ً
–Y‚ꂽ‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢‚ھپA•نگو‚ة‚غ‚آ‚è‚ئ‚àگ¶‘ج”½‰‚ھ‚ب‚¢‚ج‚ة‚حŒ©’ت‚µ‚à
”كٹد“I‚ة‚ب‚éپB
–Y‚ꂽ‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢‚ھپA•نگو‚ة‚غ‚آ‚è‚ئ‚àگ¶‘ج”½‰‚ھ‚ب‚¢‚ج‚ة‚حŒ©’ت‚µ‚à
”كٹد“I‚ة‚ب‚éپB
پ@‚©‚‚µ‚ؤ—[“ْ‚ح’¾‚ف‘D‚ةژOگFƒ‰ƒCƒg‚ً“_“”‚·‚éپB•س‚è‚ة‚¢‚½10ƒpƒC‚ة‹ك‚¢
’ق‚è‘D‚حٹFپA‚ي‚½‚µ‚ً‚ج‚¯ژز‚ة‚µ‚½‚©‚ج‚و‚¤‚ةپA‚ا‚±‚©‚ضژp‚ً‚‚ç‚ـ‚µ‚½پB
’ق‚è‘D‚حٹFپA‚ي‚½‚µ‚ً‚ج‚¯ژز‚ة‚µ‚½‚©‚ج‚و‚¤‚ةپA‚ا‚±‚©‚ضژp‚ً‚‚ç‚ـ‚µ‚½پB
‚ـ‚ء‚½‚’ق‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚ي‚¯‚¶‚ل‚ب‚¢پB’†Œ^‚جƒAƒW‚R•CپB‚©‚ê‚à‚»‚ج’ِ“x‚إ‚ي
‚½‚µ‚ج‚ً‚©‚ê‚جƒNپ[ƒ‰پ[‚ة•ْ‚èچ‚قپB
‚½‚µ‚ج‚ً‚©‚ê‚جƒNپ[ƒ‰پ[‚ة•ْ‚èچ‚قپB
پu‚س‚½‚è‚â‚©‚炱‚ê‚إڈ\•ھپv
ٹً‚µ‚»‚¤‚ة—ç‚ًŒ¾‚ء‚½پB‚µ‚©‚µپA‚ي‚½‚µ‚ة‚ح‰ئ‘°‚س‚½‚è‚â‚©‚çپA‚Rگl‚â‚©‚ç‚ج
–â‘è‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB
–â‘è‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@’ق‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‹•‚µ‚¢پB‚ب‚؛’ق‚ê‚ب‚¢“ْ‚إ‚ ‚ء‚½‚ج‚©پA——R‚ھ‚ي‚©‚ç
‚ب‚¢‚±‚ئ‚ھ‰÷‚µ‚¢پB”و‚êپA“{““‚ج‚و‚¤‚ةŒ¨‚ة”w’†‚ةچک‚ة‚¨گK‚ة‚س‚‚ç‚ح‚¬
‚ةپB
‚ب‚¢‚±‚ئ‚ھ‰÷‚µ‚¢پB”و‚êپA“{““‚ج‚و‚¤‚ةŒ¨‚ة”w’†‚ةچک‚ة‚¨گK‚ة‚س‚‚ç‚ح‚¬
‚ةپB
پ@‚±‚ج“ْپAŒ»ژہ‚جŒµ‚µ‚³‚ھ‚ي‚©‚ء‚½‚ج‚ح‚ذ‚ئ‚è•l‚؟‚ل‚ٌ‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB
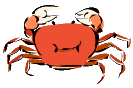
|
|

